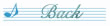27
自分と自分との約束
柚が湯船から出てきたのは30分後。のぼせる寸前だったが中野に話を聞けてよかったと
思った。
「おや、ずいぶん長かったねぇー。かわいそうにおばばにつかまったんだね」
番台にいた人が大声で言った。中野は番台をにらみつけた。
「誰がおばばだい!」
「中野さん?」
男湯の脱衣所から声がした。柚の父親の声だった。
「ああそうだよ。あんたの娘はいい子だね。あんたに似て」
「ありがとうございます」
「何がありがとだよ!!もうとっくに出て、牛乳も飲んだあとじゃないか。ったく何のために銭湯
に来てるんだよ。湯冷めしたら元もこうもないだろうが。もう一度入っておいで」
に来てるんだよ。湯冷めしたら元もこうもないだろうが。もう一度入っておいで」
「じゃそうさせてもらいます。柚―お父さんもう一回入ってくるな」
「はーい」
番台をはさんでの会話、柚はさっき中野から聞いたことを思い出してくすくすと笑った。そして
カバンからタオルをだして髪と体を拭いて服を着た。いつも三好家には家に帰る前に寄るので
下着とタオル数枚だけはいつも常備していた。
下着とタオル数枚だけはいつも常備していた。
「おや何がおかしいんだい?」
「さっきおばさんが言ってたことがそのままだから」
「おやおばさんかい?」
中野は嬉しそうに頬に手を当てた。
「何がおばさんだよ!おばば。いやおばあだね!あんたはもう!!」
「何だって!!じゃお前はぶたかい?そんなお腹して!」
2人の言い合いを見て、柚は自分と卓真のような会話を見ている気がした。
「(卓真と私みたい。なんだかんだ言って、卓真としかあんな会話できないもんね)」
そして服を着た後肩にタオルをかけてそこにあった長いすに腰掛けた。
「はい」
「なんですか?これ」
「ひやしあめ」
「ひやしあめ?」
そこに中野がやってきて、小さな瓶を渡した。柚はそれを受け取って、じっと見た。
そしてふたを開けた。
「甘いけど私は好きなんだ」
「このばばあ毎日それ飲んでるんだよ。だからうるさいくらい元気なんだ」
番台からまた口を挟んできた。
「うるさいよ!!」
そう言って中野はひやしあめを口に入れた。柚もそっと口に入れた。
「どうだい?」
「んーよくわからないです」
「ハハハ、若いもんにはおいしくないかもしれないねぇ」
「なんか甘いのか辛いのかよくわからない」
「ハハハ、生姜が入ってるからね。甘いのははちみつが入ってるからだよ。
昔は冷やしたものをひやしあめ。温かくしたものをあめゆと言ってよく飲んだものだよ」
そう言って中野はまた飲み始めた。柚も少しずつながら口に入れた。そして、飲み終わる頃に
は髪の毛はもう自然乾燥していた。
は髪の毛はもう自然乾燥していた。
「じゃまたおいでよ!!」
父親が二度風呂から出てきたので、柚は番台と中野に別れを告げて銭湯を後にした。
「どうだった?」
「すごく楽しかった。中野さんとも仲良くなれたし」
「そっか。元気になったか?」
「うん!ありがとう。ねぇお父さん、お父さんは自分自身に約束があるの?中野さんがそうじゃ
ないかって言ってたの」
ないかって言ってたの」
「んー約束かぁ・・・あるのかもしれないな!柚、お父さんが家で仕事しないわけわかるか?」
「それが約束?」
「お父さんは家ではお父さんでいたいからだよ。だからお父さんは家で仕事しないんだ。
たとえ帰りが遅くなって、お前たちと話せなくてもお父さんは家ではお父さんでいたいんだ」
「そう・・・なんだ」
「ここの銭湯はけっこう前から毎日来ててさ。お父さんの癒しの場。みんなには少し遠いから
内緒にしてたんだけどな。三好さんには口裏合わせてもらっていたんだ」
柚と父親は帰り道を歩きながら話した。風が心地よかった。駅まで着くと柚の表情は晴れ晴れ
していた。そして電車に乗り込むと柚は中野の話を思い出しながら眠りに入った。
していた。そして電車に乗り込むと柚は中野の話を思い出しながら眠りに入った。
「じゃあさっきの続き話そうか。私には昔、好いた人がいたんだ。けどね、その人には許嫁が
いたんだよ。私はそれでも好きだった。でもその人には『忘れてほしい』って言われてどうしよう
もなかったんだ。もうその人には何を言っても無駄だった。だから私は自分に約束したんだ。
もなかったんだ。もうその人には何を言っても無駄だった。だから私は自分に約束したんだ。
その思いを口には出さないって。でもその代償にその人を思い続けた。するとね、心が軽くなっ
たんだよ。自分だけがそれを認めているからね」
たんだよ。自分だけがそれを認めているからね」
「自分だけが認めている?」
「そう。口には出さないが、私はその人が好きだった。身近な存在だったから顔を合わせること
も度々あって最初は辛かったよ。でも自分だけがその人を好きなことを認めていたんだ。自分
にだけは嘘つかないでね。だから私は救われた。もし無理して自分にも嘘をついていれば、
も度々あって最初は辛かったよ。でも自分だけがその人を好きなことを認めていたんだ。自分
にだけは嘘つかないでね。だから私は救われた。もし無理して自分にも嘘をついていれば、
私は壊れていただろうからね。だから代償付きで約束を作ったんだ」
柚はそれを聞いて自分も約束しようと心に決めた。『夏柘にもう自分の気持ちを告げるような
ことはしない』と。そして思う自分の中で思うことが代償だとそう決めた。
「おはよう!」
「おはよう!!柚」
「あ、私夏柘のこと諦めることにしたの!これからは私、銭湯のこと頑張ることに決めたから」
「は?柚、お前ちょ、ちょっとこっち来いよ!」
翌日、柚がリビングに行くと圭と明海が昨日のことを聞こうと目を輝かせてわくわくしていた。
しかし、柚から返ってきた言葉は予想外の一言だった。圭は顔色を変えて柚の腕を引っ張り
柚の部屋に連れて行った。
「どういうことだよ?」
「どういうことって?」
「意味がわかんねぇ!ちゃんと説明しろよ!!」
「決めたの!私がそういう風に」
「夏柘に何か言われたのか?」
「違う!!そんなんじゃないの!私が決めたの!だから圭にい・・・もう何も言わないで」
圭は納得がいかなかったが柚のあまりにも真剣な目と決意に何も言うことが出来なかった。
「・・・わかった」
「ありがと圭にい」
「おはよう!」
「おはよう柚」
「よ!柚!!」
銭湯にはもう夏柘と卓真がいつものように来ていた。圭はのど元まで出かかった言葉を
そっとしまった。柚と夏柘には何の変化も見られなかったからだった。
「さて!今日から頑張らないとね!!残り2週間だもん!!」
「頑張ろう!!」
こうして柚の思いは柚の、柚だけにしか開けることのできない心の大事な宝石箱に
しまわれた。いつか、いつか開けることが出来るようになるその日まで。