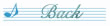26
嫌なことは忘れなくて水に流そう
夏柘の突然の言葉それは紛れもなく、柚の心を貫き、こなごなにした。どうして、何で?
そんな言葉をひたすら叫んでも夏柘はただごめんとしか言わない。柚はいたたまれなくなり、
荷物を持って飛び出した。もらったCDは置いて。
「柚!絶対に今日のことは誰にも言わないでね!それから今の言葉意識して、
気まずくならないで」
夏柘は柚が飛び出したときもそんな言葉しかかけなかった。柚は目の前が真っ暗になり、
夏柘の家を出て少し離れたその場でうずくまって泣いた。誰が見ていようとかまわなかった。
そして、そんな柚にふと声をかけてきた。
「柚?柚なのか?」
「お、お父さん?」
柚が顔を上げてみるとそこには父親がいた。
「どうしたんだ?何かあったのか?」
父親の勤める小学校は夏柘の家からそんなに離れてはいなかった。父親は仕事を済ませ、
帰宅するところだった。
「お、とう、さん」
柚はそう言うと父親の胸に泣きながら飛び込んだ。
「あ、もしもし、あ、俺だけど、今、柚と会って、ちょっと寄り道して帰るから」
父親は泣きじゃくる柚を家に帰ろうと説得するものの柚はただ首を横にふるばかり。すると
家に連絡を入れて、駅のほうに向かった。
「ど、どこか行くの?」
それまでは何も言わなかった柚が駅に着く寸前に口を開いた。父親は柚に笑顔を返し、
「元気のでるとこ行こう!!」
そう言って駅に着くと券売機で切符を2枚買った。
電車に乗り込むと柚はまた口を固く閉ざした。口を開けば夏柘に口止めされたことを言って
しまうかもしれない。そう思った。しかし、さっきより少し安心感はあった。何も聞かずそっと隣
にいてくれる大好きな父親がいるから。電車はいくつも駅を通過した。
にいてくれる大好きな父親がいるから。電車はいくつも駅を通過した。
「柚、次の駅で降りよう」
電車が駅に到着して、2人は降りた。柚の乗った駅から10個目の駅。ネオンライトも少なくて
町が眠ってしまったみたいに見えた。父親は立ち止まり何も言わず、柚にそっと400円を渡し
た。柚は黙ってそれを受け取る。そしてまた笑って歩き出した。柚はその後をついていった。
町が眠ってしまったみたいに見えた。父親は立ち止まり何も言わず、柚にそっと400円を渡し
た。柚は黙ってそれを受け取る。そしてまた笑って歩き出した。柚はその後をついていった。
「お父さん、どこに行くの?」
もう柚の涙は乾いていた。
「元気の出るとこだよ」
「どこ?」
「ついてきたらわかるよ」
そう言って父親は足を止めず答えた。そして10分くらい歩くと父親がある場所で足を止めた。
「ここ?」
「そう!ここだよ」
そこは一つの銭湯だった。まるで風貌はあの銭湯と同じ。柚はまた思い出しそうになった。
でも父親は中に入っていった。
「じゃ、出たら外で待っているから」
「お父さん!私・・・」
入りたくない。そう言おうとしたときにはもう父親は男湯に入っていた。柚はためらったが辺りに
は灯一つない。そしてこみ上げてくる悲しみをそっと胸に抱きつつ靴箱に靴を入れて、女湯の
扉を開けた。
は灯一つない。そしてこみ上げてくる悲しみをそっと胸に抱きつつ靴箱に靴を入れて、女湯の
扉を開けた。
「いらっしゃい!!あ、あんただね?相河さんの子供って。250円だよ」
番台に座っていたのは恰幅のいい一人の中年の女の人だった。柚は番台を見上げてさっき
もらったお金を渡す。その人は笑顔でお金を受け取った。
「あんたのお父さんよく来てくれるんだ。毎日のようにね。もうこんな銭湯数数えるくらいしか
ないしね」
柚が服を脱ぎ始めるとその人はそう言った。脱衣所にいたのは柚だけだったが中には何人か
人影が見えた。
人影が見えた。
「こんなすたれた銭湯、客足も減ってだめだめだけどね。あんたのお父さんはこういってくれた
んだよ『おばさんの顔見てると元気になれる。毎日ここに来るのが楽しみだ』って。
んだよ『おばさんの顔見てると元気になれる。毎日ここに来るのが楽しみだ』って。
こんな銭湯でも楽しみにしてくれている人がいるんだなって思ったよ」
「そう・・・なんですか」
「昔はさ、そう言ってくれる客も多かったんだ。銭湯に来るといやなこと忘れられるってね。ほら
嫌なことって水に流すって言うだろ?家の風呂じゃ流しきれないことだってある。だから銭湯に
来て水に流すんだ。ってあ、ごめん早く入りたかっただろ?」
嫌なことって水に流すって言うだろ?家の風呂じゃ流しきれないことだってある。だから銭湯に
来て水に流すんだ。ってあ、ごめん早く入りたかっただろ?」
「あ、すいません」
「中に一人おばばがいるけど気にしないでおくれよ」
ガラっ
柚は扉を開けて中に入っていった。
「あらあんた新人さんかい?若い子が来るのは嬉しいよ」
「どうも」
「ここの銭湯はどんな薬よりも効く特効薬だよ!なんせ番台があれだからね」
柚が中に入るとシャワーのところに座っていた60くらいの女の人が声をかけてきた。また
何か嫌味を言われるのかもしれない。でもその女の人は笑ってそう言った。柚はその人に
手招きされて、隣に座った。
「あんたどこから来たの?」
「五香です」
「あらー遠いとこから来たんだね」
「父親に連れられて」
「あー相河さんの娘さんかい。あの人とは番台をはさんだ銭湯仲間なんだよ。
私は中野と言います」
「お父さんいつも来てるんですか?」
「うん。来てるよ」
「いつも、ですか?」
柚はそう言うとシャワーをひねりお湯を出して、髪を洗い始めた。中野と言った女性が体を
洗い始めたからだった。
「そうそう、家の風呂が狭いらしいね。さしずめ新幹線の扉のところみたいだってぼやいてた
よ。でも、改装してんだろ?家の風呂が広くなったらあんたもお父さんもここには来なくなるんだ
ね」
よ。でも、改装してんだろ?家の風呂が広くなったらあんたもお父さんもここには来なくなるんだ
ね」
最初は笑っていたが中野は少しさびしそうに体を洗いながら言った。柚は髪を洗い終えて
シャワーを止めた。
「お父さん、いい人だねぇ。でもいい人すぎるから疲れるんだろうね。だからここに来てゆっくり
心も体も休ませてあげてるんだろう」
心も体も休ませてあげてるんだろう」
「お父さんいつも帰ってくるのが遅いんです。仕事をいつも最後までやらないと帰ってこない
から。だから私、お父さんのこと・・・何も知らない・・・」
「そうかい。きっとそれはお父さんの約束なんだろうね」
「約束?」
「お父さんがお父さんの中で決めた約束。私も昔自分に約束したよ。たとえ認めてもらえなくて
も自分の中で絶対に決めてたことあった。おや長話が過ぎたね。体が冷えてきたよ。そろそろ
湯船に浸かるかな」
も自分の中で絶対に決めてたことあった。おや長話が過ぎたね。体が冷えてきたよ。そろそろ
湯船に浸かるかな」
「その続き教えてください。私も体洗ってすぐに湯船に行きますから」
中野は頷いて湯船に向かい、柚は体を洗い始めた。そして体を洗って、中野のところに行っ
た。
た。
「おや早いね」
「失礼します」
そう言って柚は湯船に足を入れた。温度は少し熱いくらいだったが我慢して全身浸かった。
「あつっ!」
「アハハ、少し若い子には熱いかもしれないね」
「だ、大丈夫です。それより・・・さっきの続き・・・お願いします」
肩まで浸かって少し無理をしていたが柚はどうしても中野の話が聞きたかった。中野はゆっくり
と口を開く。柚は火照る体にムチを打って耳を傾けた。
と口を開く。柚は火照る体にムチを打って耳を傾けた。