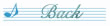第三部
18
ビーフコロッケとアニマルマン
あれから圭と卓真が帰ってきて、みんなはそれぞれ帰宅することになった。卓真の母親は
自分が出した答えだとわかっていながらも最後の夏柘の言葉に切なさを感じていた。
「よかったのよね」
「・・・よかったよ」
帰り道、ぽつりとつぶやいた一言に卓真は返事を返した。2人はゆっくり歩いた。
卓真は照れていたのか母親から歩幅一つ分の距離を空けて。
「・・・あの子ほんとによく似てたわ。似すぎるくらいね」
「・・・父さんに?」
「そう。とってもよく似てた。だから惹かれたのかもしれないわね。・・・私ね夏柘が小学生だって
ほんとは知ってたのよ」
ほんとは知ってたのよ」
「えっ?」
「偶然ランドセル背負ってるとこ見てね。でも一生懸命に高校生を演じてた夏柘が可愛くて
ずっと知らないふりを通してたの」
「そう・・なんだ」
辺りはもう真っ暗。街頭もあまりなく、空の星が2人を照らしていた。母親は立ち止まって
上を見上げた。夏柘と見たあの日の満天の星空を思い描くかのように。
「ここで星見れてよかった」
「俺も」
「ねぇー夏柘、また星見に来ようね」
「そうだね」
あの日交わした会話が鮮明に蘇ってくる。そして、その言葉は同時にもう一つの思い出に
変わっていた。
「またこような」
「うん」
「俺、お前と見れてよかった」
「私も」
同じような会話を卓真の母親は交わしたことがあった。そう、それは卓真の父親と。
「もしあの人が生きてたら、私夏柘のこと好きにならなかったのかもしれないわね」
「・・・それはわからないと思うけど。夏柘は父さんの生まれ変わりかもしれないんじゃない?
そんなに似てるなら」
卓真の父親は卓真が5歳の頃交通事故で他界した。卓真の両親は幼なじみでいつも互いが
かけがえのないパートナーだった。だから母親は父親が他界したとき、自らの命を絶とうと
かけがえのないパートナーだった。だから母親は父親が他界したとき、自らの命を絶とうと
した。それを止めてくれた相手が現在の卓真の父親だった。
「そうね。そうかもしれないわ。でも・・・私、ちゃんと夏柘のこと好きだったわよ。
あの人に重ねてただけじゃなくて」
「だと思う。だから・・・夏柘をふったんだろ?重ねてただけならまだ付き合ってたと思う」
「そうねぇーでも卓真とお父さんが今の私の家族なんだってあの男の子に教えられたって
いうのもあるわよ」
「柚のいとこだっけ?」
「そう。でも人に教えられるほど、私はだめだったのね」
「それは俺も親父も母さんに構ってなかったからだって。確かに冷えてたあの家庭は」
「彼に救ってもらえたわね。これからは惜しみなく卓真とお父さんを愛していくからね」
卓真の家庭は冷えていた。卓真は反抗期を迎えて、特に母親に対しての態度はひどいもの
だった。口は利かない。部屋に閉じこもる。ひどいときはご飯ですら自分で勝手に買って食べて
いたときもあった。新しい父親は仕事人間でいつも帰りが遅い。卓真の母親は心の拠り所を
いたときもあった。新しい父親は仕事人間でいつも帰りが遅い。卓真の母親は心の拠り所を
失っていた。そんなときに夏柘と出会い、いつしか彼を自分の心の拠り所にしていたのだった。
「気持ち悪い」
「なーにが?」
「よってくんなよー」
「卓真―あいしてるわよ!!あ、そうだ!明日はお父さんの好きなビーフコロッケにしましょう」
母親は卓真に後ろから腕を肩に回して抱きついた。前までの卓真なら出来なかったが彼の
反抗期はいつしか終わりつつあったので言葉は否定するも内心嬉しい気持ちがあった。
自分の母親が本当にそこにいるということに実感できたことに。
「ねえ圭にい、どうしてさっきあんなにむきになったの?」
柚は夕食を済ませ、ソファでくつろぐ圭の隣に座り、ぼそっと尋ねた。圭は真剣にやっていた
テレビの番組にかじりついていたので柚の声が聞こえていなかった。
「ねえ圭にい」
「おい柚!!お前『動物の男の人が食べたら死ぬ食べ物』分かるか?」
少し張り上げた声でもう一度柚は圭に尋ねた。すると圭から返ってきた返事はちょうど圭が
見ていたテレビ番組でさっきやっていたクイズだった。柚はちょっとと言うがしばらく、その答え
を考えた。そして・・・
を考えた。そして・・・
「動物の男の人って・・・動物はアニマルだから・・・アニマルマン???」
「は?あ、アニマルマン?お前何言ってんの?明海正解教えてやれよ」
そう言った圭の言葉は今にもふきだしそうだった。圭はさっき一緒に見ていた明海に正解を
ゆだねた。
「柚―アニマルマンってなんだ???正解は・・・動物の男は『おす』だから『おす』が死ぬから
『おすし』だぜ!!」
『おすし』だぜ!!」
明海がそう言うと圭は堪えていた笑いが一気に溢れてきた。
「アーハッハッハッハ!!だめだもう限界!!アニマルマンとかありえないぜお前」
「な、何よ」
「ほんとに柚は可愛いなあ」
そう言いながら圭は柚の頭を撫でた。柚はその手をすぐふり払って口を膨らませる。今日一日
柚の呼び方はアニマルマンになったのだった。そしてすっかり柚は圭に尋ねたかったことを
柚の呼び方はアニマルマンになったのだった。そしてすっかり柚は圭に尋ねたかったことを
忘れてしまっていた。
翌日、いつものように柚は明海とそして圭と銭湯に行く準備をしていた。
「じゃぁそろそろ行きましょうか」
「オレ後でママと一緒に行くぜ。今日は朝美帆ちゃんと会う約束してるから」
「お前デートか??」
「そうだぜ。だから後からママが買い物行くときに送ってもらうぜ」
「あっそ分かったわよ。じゃ、行こう圭にい」
朝からデートだという明海を置いて、圭と柚は銭湯に向かった。
「じゃあね明海くん」
「おう!またデートしようぜ」
明海は朝の間美帆と楽しく遊んでいた。そして、美帆と別れて、母親と一緒に銭湯に向かって
歩いていた。銭湯が見えるところまで行くと、明海は母親と別れ一人で銭湯に向かっていた。
歩いていた。銭湯が見えるところまで行くと、明海は母親と別れ一人で銭湯に向かっていた。
手にはちゃんと明海秘密道具が入ったカバンを持っていた。
「ねぇーボク、ちょっと聞きたいことがあるんだけど」
銭湯の入り口までほんのわずかな距離まで行くと、明海に一人の少女が声をかけてきた。
制服を着ていたその彼女は肩までの髪をしていて、目がパッチリしている。
「なに?」
「この近くに銭湯はないかな?」
「銭湯?ならオレが今から行くから案内してやるよ」
「ほんとに?ありがとう」
少女は明海にお礼を言って明海の手を握る。そして明海はその少女を連れて、
銭湯に行った。
「柚―お客さん連れてきたぞ」
「お客?あんたのれんも出してないのに誰連れてきたのよ」
玄関で明海が大声で柚を呼ぶとぶつぶつ言って扉を開け、柚と圭が中から出てきた。
「圭・・・・」
「裕歌・・・・」
圭と少女は目を合わせると互いの名を呼び合った。