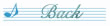14
来客と明海の約束
柚は自分の部屋に戻り、やっと我に帰っていた。勢いで告白したものの実際恋などしたことが
ない。小学生のときにお返し目当てでクラスの男子にチョコレートを配ったことくらいしか経験が
ない。あー言ったものの自分がどうやって夏柘を振り向かせるのか。そしてあんなことを言って
しまってこれからどう夏柘と接すればいいのか。考えることがいっぱいでまたふとんにもぐり
ない。小学生のときにお返し目当てでクラスの男子にチョコレートを配ったことくらいしか経験が
ない。あー言ったものの自分がどうやって夏柘を振り向かせるのか。そしてあんなことを言って
しまってこれからどう夏柘と接すればいいのか。考えることがいっぱいでまたふとんにもぐり
こんでしまった。
「最近柚さんは布団が大好きなのね」
「・・・・」
毎度のことのように布団の中にもぐりこんでいる柚に母親も呆れて気にすることもなくなった。
洗濯物を持って部屋の中に入ってきたが、声はかけるものの何があったなど聞いてくることは
なかった。
洗濯物を持って部屋の中に入ってきたが、声はかけるものの何があったなど聞いてくることは
なかった。
「あ、そういえば、明日圭くんが来るって電話あったわよ」
「え!?圭にいが来るの!?」
「圭がくるのか?」
その声を聞きつけて、明海が柚の部屋に入ってきた。そんな大声で母親も言ったわけではな
いがこの相河家の柚と明海は、“圭”という言葉に敏感に反応するのだった。
いがこの相河家の柚と明海は、“圭”という言葉に敏感に反応するのだった。
「圭にい来るんだーすごい楽しみ」
さっきまで落ち込んでいた柚も彼の名前を聞いて、喜びの表情に変わっていた。だが、明海は
逆にいつもとは違い、静かになった。
逆にいつもとは違い、静かになった。
翌日、いつもなら元気に飛び起きてくるはずの明海が鎮痛な面持ちで起きてきた。
「柚―オレ今日銭湯行かないぜ。頭痛い」
「え?!ちょっと待ってよ!!明海が行かなかったら私行きにくいでしょう!!」
「・・・ごめん。オレ今日は行かない」
そういうと、明海は部屋に戻って行った。柚はさすがに昨日あれだけ罵声を浴びせた以上休む
わけにもいかないと思ったがなんとなく行きづらい気持ちがあったので、悪いと思いながらも卓
真に電話をかけた。
わけにもいかないと思ったがなんとなく行きづらい気持ちがあったので、悪いと思いながらも卓
真に電話をかけた。
「・・・今日2人だけ?」
「なんか明海が頭痛いらしくて柚が看病するんだってさ」
「・・・ふうん」
ここは銭湯。卓真と夏柘の2人しかいない。なんともいえない空気が漂っている。卓真も夏柘も
必要以上に言葉を発さない。沈黙の中、2人はどちらが言うでもなく、掃除を始めた
必要以上に言葉を発さない。沈黙の中、2人はどちらが言うでもなく、掃除を始めた
昼が過ぎて相河家に一人の来客が来た。母親は買い物で出払っていたので、柚が対応した。
「圭にい!待ってたのよーいらっしゃい」
「よ!柚元気にしてか?」
「うん!元気よ。入って、入って」
「じゃ、おじゃまします」
この来客こそ、前日柚が大騒ぎして、今日、明海が元気のない理由となった圭にいこと吉原圭
だった。圭は柚と明海の従兄弟にあたり、現在男子校に通う高校2年生である。
だった。圭は柚と明海の従兄弟にあたり、現在男子校に通う高校2年生である。
「あれ?明海はどうした?」
「んーそれが・・・」
圭は家に上がり、最初に明海の姿を捜した。しかし、明海は部屋から出てこない。柚は、渋い
顔をして、圭を明海の部屋の前に連れて行った。
顔をして、圭を明海の部屋の前に連れて行った。
「明海―圭にい来たわよ!入るね」
「だめだ!!」
明海から返ってきた返事は拒絶の返事だった。柚はひとまず今は出てこないと圭に言って、
リビングに彼を通した。
「ごめんね圭にい。なんか明海朝から頭痛いみたいで・・・」
柚はお茶を入れながらそう言った。
「そっか。あ、今、お前ら銭湯の掃除してるんだろ?」
「うん」
「けっこう頑張ってるみたいじゃん」
「そうよ。毎日頑張ってるわよ」
「・・・・俺やっぱ気になるから明海のとこ行ってくるわ」
圭はそう言うとお茶を一気に飲み干して、明海の部屋の中に許可もとらず入って行った。
「圭?!」
「よ!明海」
「勝手に入ってくるなよ」
「お前、俺が来るから怯えてたんだろ?」
明海が朝から様子がおかしかったのは圭が来ることが原因だった。明海が圭を恐がる理由
それは・・・。
「オレ圭との約束まだ守れてないんだ」
「・・・そうか」
「柚を守れって言われたのにオレ何もできてない」
「そんなこと気にしてたのか?」
明海は姉と同様、布団をかぶりながら話した。圭はベットにもたれるように座る。
「オレあの日、圭に言われたこと何も・・・」
「聞いたぞ、お前ちゃんと柚を守ってるじゃないか」
「え?!」
明海は圭のその一言に思わずふとんから出てきた。圭は日に焼けた顔をしていて、白い歯を
見せて笑う。
見せて笑う。
「バカだなーお前、そんなこと気にしてたのか」
明海は圭に飛びついた。そして彼の胸の中で泣いていた。圭は優しく抱きしめて、明海の頭を
そっと撫でた。
そっと撫でた。
1年前、明海は今のような子ではなかった。可愛がられることが当たり前、わがままを聞いて
もらえることが当たり前の極普通の子供だった。
「あっくん、きょう、ハンバーグ、たべたい」
明海がそう言えば、母親が甘やかし、作る。明海の両親は明海が可愛くて仕方なかった。だか
ら彼をとても甘やかして、育てていた。しかし、それに伴ってか柚が反抗期を迎えた。家に帰る
と常に母親は明海につきっきり。ひどいときは柚を無視することもたびたびあった。
ら彼をとても甘やかして、育てていた。しかし、それに伴ってか柚が反抗期を迎えた。家に帰る
と常に母親は明海につきっきり。ひどいときは柚を無視することもたびたびあった。
柚はとうとう我慢の限界を迎えて、明海に対して、暴力を振るいかけた。それを恐れて母親は
丁度、一年前の夏休み、柚を圭の家に預けようとした。でも、圭はそこで・・・
丁度、一年前の夏休み、柚を圭の家に預けようとした。でも、圭はそこで・・・
「俺、明海を預かる」
当時はまだ3歳の明海、一番手がかかることから猛反対を受けた。だが、圭は明海を可愛が
りすぎるから柚が離れていくことを察していたので、まずは柚と話し合うべきだと無理やり一ヶ
月明海を自分の家で預かった。
りすぎるから柚が離れていくことを察していたので、まずは柚と話し合うべきだと無理やり一ヶ
月明海を自分の家で預かった。
それから一ヵ月後、明海は今のようにヒーローを気取るようになった。
「お前、よく頑張ってるよ!柚のことちゃんと守ってる」
「そんなこと」
「いや、前のお前とは全く別人だよ」
一ヶ月、明海を預かった圭は自分にしつけをさせてほしいと圭の両親に言い、自分の部屋で
明海を預かった。圭は明海に対して、甘やかすようなことはしない。着替えから何から自分の
出来ることは自分でしろと言いほしい物はすぐ手に入れるのではなく、頑張ってから手にすると
か。
出来ることは自分でしろと言いほしい物はすぐ手に入れるのではなく、頑張ってから手にすると
か。
明海が今、フルーツ牛乳が大好きなのもそれである。圭は自分の小遣いから何か頑張るごと
に明海にジュースをご褒美としてあげていた。そして、明海が圭からもらったジュースで一番好
きだったのがフルーツ牛乳だった。
に明海にジュースをご褒美としてあげていた。そして、明海が圭からもらったジュースで一番好
きだったのがフルーツ牛乳だった。
「ちゃんと今明海が頑張ってるの聞いてるから俺、褒めにきたんだぜ」
「本当か?」
「あー俺の言いつけお前ちゃんと守ってるし、約束だって」
圭と明海の約束。それは・・・『お前は男として柚を守れ!!』だった。圭はちゃんと柚が苦手な
ものから守ってあげたり、夏柘が泣かせたときに夏柘を叱りつけたこともちゃんと知っていた。
ものから守ってあげたり、夏柘が泣かせたときに夏柘を叱りつけたこともちゃんと知っていた。
それは柚が『明海がお前を守ったら連絡してこい』と圭に言われて連絡していたからだった。
そう、今紳士的な明海がいるのはすべてこの男、吉原圭のおかげだったのだった。
「ありがとう圭」