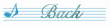11
元々恵まれていたとは思えない。でもそれでも幸せだと思った。
俺の傍にはいつもあいつがいたから。
俺の親は共働きで常に家には俺と妹の未彩(みさ)しかいない。
おかげで家事は完全に出来るようになった。
親の愛情を受けなかった俺にとって未彩は何よりもかけがえのないものになっていった。
「おにいちゃん」
そう呼ぶあいつが可愛くてもう俺はあいつ以外誰も目に入らなかった。
女としてしか見てないって気付いたのはいつだろうか。
俺たちが中学に入ってからすぐかもしれない。
年子の未彩は俺が言うのもなんだがとても大人っぽかった。
俺と同学年のやつらよりもはるかに上に見えた。高校生くらいに。
だから男が寄ってたかってきてそれを見てイライラを募らせたことを覚えている。
でもこんな気持ちは必要ないと思った。俺はあいつの兄貴だから・・・。
「え?どういうこと・・・ですか?」
そんなある日だった。めずらしく日曜日俺の家に電話が鳴る。
未彩は今日友達と出かけてくると言ってたから誰も出ないだろう。
最初は鳴り続ける電話を無視していたがあまりにもしつこく鳴るので受話器を取った。
・・・嘘だろ。そこから聞こえてくるのは棒読みとも取れる事務的な言葉。
だがその一つ一つが俺の心を貫いた。
「そちら辻宮未彩さんのお宅でしょうか?私、福地総合病院のものなんですが
・・・辻宮未彩さんが・・・交通事故でこちらに運ばれてきまして・・・未彩さんなんですが・・・
『即死』でした」
何言ってるんだ?俺の頭の中が真っ白になる。
信じたくない。信じられるわけがない。
それでも俺しか行くやつがいない。
親に連絡をすればどちらの携帯にも繋がらなかった。
急いで必要なものだけを準備して病院に向かった。
「・・・未彩」
横たわるベッド。
白い布が掛けられていてそれをそっと取ると朝見た顔と同じ顔が俺の目に映る。
この顔だ。俺が愛してしまった女の顔。
ただ違うのはもう二度と目を覚まさないということ。
ゆすってもたたいても二度と開かない瞳。二度と聞けない俺を呼ぶ声。
「未彩!!」
俺の二つ並んだ瞳から流れるもの。こんなものいらない。
こんなもの流れなくたっていいから。
未彩を、未彩を返してくれ。誰が奪ったんだ。俺の未彩を・・・。
葬儀や通夜には親も参列した。悲しそうな瞳をして涙を流してる。
どうせほとんど顔も知らないくせによくそんなことができるな。
誰もいなくなると俺は棺を開けた。未彩。俺の愛する人。
最初で最後の口付けを交わしてもいいか。
冷たくなった未彩の唇に自分の唇を押し当てた。そしてゆっくりと棺にふたをした。
「それ本当か?」
「・・・はい。未彩の服はびりびりに破かれていました」
「誰だ?そいつ誰か知らないか?」
「・・・同じクラスの・・・」
何もかもを終えた後、俺は未彩と会う約束をしていた友達に呼び出された。
その話を聞いて俺はそいつを殺そうと思った。
未彩を奪ったんだから死んで当然だ。
未彩は友達との約束の場所に行こうとして同じクラスの男子に襲われた。
嫌がる未彩を無理やり・・・。
そしてそれから必死で逃げようとして事故に遭った。
それを友達は本人から聞いたという。
「・・・教えてくれてありがとう」
それが俺の最後の言葉になると思った。
どうせここにいたって俺は誰にも必要とされるわけじゃない。
だったらいっそあいつを殺して俺も死のう。
怖くはなかった。でも何も持っていかなかった。
俺が俺の手でそいつを殺りたかったから。
向かった先に見えたのは人間なんかじゃなかった。もう俺には人の形をした悪魔にしか。
それからのことは覚えていない。とにかく殴った。それだけ。
でもあいつも俺も死ななかった。
俺は警察に捕まった。でもすぐに釈放された。
親が金を払ったから。一生ここにいたほうがよかった。
どうせなら死ねたらよかったのに。俺はもう誰も見えなくなった。
見境なく人を殴り、俺の拳は血で汚れてた。
周りからは喧嘩の百戦錬磨と言って恐れられ、颯太以外友達もなくなった。
それでも殴らずにはいられなかった。
あの人に出会うまでは・・・
「未彩・・・なんでお前が死んだんだろうな。俺はお前に何もしてやれなかったな。
一番近くにいたのに・・・」
「そう思うのならその血で染まった拳を彼女に見せるのはよくないんじゃないか」
行くあてもなく、気がつけば未彩が眠る墓の前にいた。
声がしたので振り返ると未彩の通夜と葬儀に来てた坊さんが立っていた。
なんだこいつ。それが俺の第一印象。俺は無視した。
「お前のやってることは正しいことか?彼女はそれで喜ぶのかのう?」
「なんだよ。うるせえな。お前に関係ないだろ」
「甘ったれんのもいい加減にせんか!!」
ばちんと音がした。俺の頬が打たれた。誰にも打たれたことなんてない。
俺はそのままその胸倉を掴んだ。
「あんたも血で染めてやろうか」
「・・・好きにしろ。だがここは彼女の前じゃ。お前はここでわしを殴れるのか?」
「・・・・」
俺はその手を放した。こんなところで殴れるわけがない。未彩が見てる。
「彼女のためにできることはそんなことじゃないじゃろ。
よいか。人は必ず死を迎える。残されるものの辛さや痛みそれははかりしれないものじゃ。
もちろんそのまま後を追うことだってある。
だが死を迎えたものが望むものはそんなものじゃない。
精一杯生きてほしい。自分の分まで生きてほしい。
それが死を迎えたものの望みじゃ。
それを叶えてやらないでいるから彼女はいつまで経っても成仏できんのじゃ」
「な、に言ってんだ」
「お前のせいで彼女は天国に行けんのじゃ。かわいそうに。
いつまでも居場所が持てずに・・・」
「未彩・・・お前そこにいるのか?」
さわさわと風が吹いた。信じられないけど俺はそこに未彩がいると確信した。
泣いているようにも感じた。
「彼女を送ってあげるか?」
「・・・どうやって?」
「お経を唱えてあげればいい。
彼女はきっとお前が心を込めてお経を唱えてあげれば成仏できる」
お経。そんなもの唱えたこともない。
そっと渡された本。漢字ばかりでよく分からない。
でも未彩。俺が悪かった。お前はずっと俺の近くで俺のやってたこと見てたんだよな。
どう思った?キスしたこと怒ったりしてるか?あいつを半殺しにしたこと怒ってるか?
人をたくさん殴って血の色に染まりきった俺だけど俺の手でお前を送ってやるから。
「・・・おにいちゃんが送ってやるからな」
へたくそだけど精一杯声を上げて本を読んだ。瞳から暖かいものが流れる。
もっとゆっくり彼女に問いかけて彼女のためにと促されてゆっくりゆっくり読んだ。
俺の言葉お前に届いてるか。ごめんな。心配ばかり掛けて。
ずっと俺を見ててくれてありがとう。
もう俺は大丈夫だから・・・だからだから未彩・・・ゆっくりゆっくり安らかに眠って。