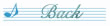Her most beloved words
あれからどのくらいの時間が経ったのだろう。
自然と離れる唇。二人は瞳を合わせた。初めての至近距離で。
「・・・どうして?どうしてこんなこと・・・」
夢中になっていたキスに翻弄される余韻を残しつつも陽菜はそう口にした。
篤貴は口を開かない。
もしかしたらこれは陽菜の夢の中なのかもしれない。
都合のいい夢。絶対に正夢にはならない。そう思った。
でも篤貴は口を開く代わりにぎゅっと力を込めて陽菜を抱きしめた。
温かい。これは夢ではない。陽菜はそう思った。
篤貴は抱きしめる腕を緩め、陽菜の手を握り、家の中に入れた。
テーブルが一つ置かれただけの一間。
そのテーブルの前に陽菜を座らせると自分も向かい合わせに座る。
篤貴はそっと口を開いた。
「・・・俺は間違っていない。あんただって便乗したじゃないか」
「あたし、そんなことを言っているんじゃない。
・・・どうしてキスしたの?って聞いてるの。あたし本気にしちゃうよ。
あなたもあたしのこと好きだって思うよ」
「・・・それも間違いじゃない。俺はあんたを見てた。
でも・・・清弥があんたのことを好きだって言ったから俺はあんたを諦めたんだ」
「・・・そっか。でもそれって・・・無理があるんじゃない?
好きだったら止められないはずだよ。
あたしがこんなこと言うのすごく変だけどあたしは清弥と付き合ったけど
やっぱりあなたが好き。だから歯止めが利かなかった」
「・・・なんで俺が好きなんだ?あんたとは接点なんてなかっただろ」
「瞳をあわせていたじゃない」
陽菜のその言葉に篤貴はびくっと肩を震わせた。
篤貴は確かに陽菜と瞳を合わせていた。
しかし、それは自分の視線に陽菜が気付いて見ていただけだと思っていた。
それがまさか彼女も故意的に自分を見ていたなんて・・・。
篤貴は陽菜をじっと見た。彼女はその瞳をしっかりと見ている。
お互いの瞳の中にお互いが映った。
「あたし、最初は全然気にしていなかった。
だけど毎日のように瞳を合わせるようになって
それが当たり前だって思うようになったの。
でも・・・夏前急にあなたが学校に来なくなった。
そして・・・夏休み明けにはもう瞳を合わせてくれなくなった。
それから清弥に告白されて・・・あなたはもうあたしに見向きもしてくれないから
・・・付き合うことにしたの」
「・・・全部清弥のためにしたんだ。
俺は・・・友達と同じやつを好きでなんていられなかった。
俺はあんたを諦めるために学校に行くのをやめた。
一応実家に帰るっていうことにして」
「実家?」
「俺、今一人暮らししてるだろ。親は転勤してさ。俺だけがここに残ったんだ。
それで親のとこに戻ってることにしてたんだ。
学校は俺が一人で暮らしてるの知ってるからな。だから考慮してもらった。
追試も受けたしな。バカだろ俺。
そこまでしたのに結局意味なかったんだぜ」
篤貴が苦笑いでそう言うが陽菜は笑み一つすら浮かべなかった。
何か飲むかと篤貴が立ち上がり冷蔵庫に向かっても陽菜はずっと黙っていた。
自分を諦めるためにそこまでしていた。
篤貴はそれほどまでに自分を思ってくれていた。
もし、自分が清弥と付き合わなければ
彼をここまで苦しめることはなかったかもしれない。
自分の一つの決断が篤貴、いや清弥という二人の人間を傷つけてしまった。
陽菜の瞳からは雫がこぼれていた。
「ど、どうしたんだ」
冷蔵庫の中から缶ジュースを2本取り出して戻ってきた篤貴の前には
溢れんばかりの涙をこぼした陽菜がいた。
そっと近寄って震える指で優しくその涙を拭う。涙は拭ってもどんどん溢れてくる。
篤貴はたまらず陽菜を引き寄せ抱きしめた。
「何で泣いてるんだ?」
「・・・あ、あたしが・・・二人を・・・傷つけた」
「あんたのせいじゃない。俺だって諦めたつもりだった。
だけどやっぱりあんたが諦められなかったんだ。
あんたと清弥が別れればいいって何度思ったかしれない」
「・・・っく・・・やっぱり無理だよね。
清弥を傷つけたのにあなたと一緒にいたいなんて」
「・・・あんた・・・槙原さんはどうしたい?俺はあんたといたい。清弥を失っても」
最初から放棄なんてするんじゃなかった。
自分の放棄も今の状況に繋がっている。篤貴はそう思った。
中途半端に諦められるほど簡単な気持ちじゃなかった。
だから夏前に一度リセットしたはずなのに。
それすらが中途半端だった。腕の中に納まるほどの小さな彼女。
その彼女が自分の取った行動でどこまで傷ついただろう。
離れようと思えば思うほど近くなる距離。
それに何より一番傷ついたのは清弥だろう。
人に頼まれると断れない性格。温和な王子様。
キスしてと言われれば断れない。付き合ってと言われれば断れない。
きっと自分も陽菜を好きだといえば笑顔で身を引いただろう。
だからこそ自分から身を引いた。
そんな優しい彼が初めて自分から好きだと言った相手だから。
抱きしめた腕をもう一度緩めその腕は掴んだまま篤貴は陽菜の目を見て口を開いた。
「・・・俺、間違ってた。清弥のためとか言って本当は自分のためだったんだ。
清弥もあんたもどっちも失わないですむって思って。
でもそんなわけなかったんだよな。俺の煮え切らない態度があんたを傷つけて、
清弥も傷つけたんだ」
「違う。あたしだよ。あなたは何も悪くない。あたしだってあなたと一緒にいたいよ。
前よりももっともっとあなたが好き。あたしの中は佐藤篤貴で占めているの」
「・・・もう一度・・・もう一度言ってくれないか?」
「え?」
「俺の名前。あんたが俺の名前言ってくれたの初めてだろ」
「・・・篤貴。篤貴。あつき・・・」
まさか涙なんて流すとは思わなかった。
愛しい人の名前がこんなに素敵なものなんて。
陽菜の乾いたはずの瞳はもう一度潤いを増してきた。
ずっと呼べなかった。その名前。
陽菜の中で封印していた一番愛しい言葉だった。
初めて口にするその名前が篤貴の心にも染み渡った。
篤貴は陽菜の存在を確認するようにまた抱きしめた。
「俺、もう手放す気ないぜ」
「・・・うん。じゃああたしも離れない。あたしは清弥と別れるよ。
・・・忘れていたけどあなたも莉那ちゃんと別れるんだよね?」
陽菜は一度回しかけた腕を回さずに篤貴の両肩に手を置いて尋ねた。
思わず篤貴も手を離す。
陽菜には清弥という彼氏がいる代わりに篤貴には莉那という彼女がいる。
自分の気持ちと篤貴の気持ちが通いあったとはいえ、
お互い恋人と別れなければならない。
陽菜はもう清弥に別れを告げる決心をした。
しかし、篤貴は一度もそんな話をしない。
今更二番目になるなんていう選択肢は考えられない。
陽菜は不安そうに篤貴を見つめた。
「それなら・・・元々俺らは付き合ってないから気にするな。
あいつにはちゃんと彼氏がいるし、俺と莉那はいとこだから。
清弥も莉那が俺のいとこだって知らない。だから頼んだんだ。
あいつにすべて話して彼女のふりをしてほしいって。
こんなこと言ったらきっと軽蔑するかもしれないけど
俺が学校に行かない間もあいつの彼氏があんたのこと教えてくれたんだぜ」
「彼氏?」
「あいつの彼氏は俺のダチ」
「もしかして竹原くん?」
「ああ」
竹原とは篤貴と陽菜がすれ違ったときに篤貴に声をかけろと言った人物。
篤貴が陽菜のことを好きだということも清弥のために身を引いたことも
彼は何もかも知っていた。
そして学校に来なくなった篤貴に陽菜の話を聞かせていたのだった。
「全部さあの二人に話してたんだ俺の気持ち。
俺があんたを好きになったときからずっと」
「・・・よかった」
「え?」
「あたし莉那ちゃんには勝てないって思ってたから。
かわいいし、あんな風にはなれないって思ってたから。
ねえ、教えて。いつからあたしを・・・好きだったの?」
陽はすっかりと沈んでしまい、街灯が灯り始めたころ
篤貴は思い出すかのようにゆっくりと口を開き始めた。