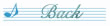Only he catches sight anymore
その日から数日、あの日決意したことを陽菜は
実行しようとはせず清弥と楽しく過ごしていた。
朝から一緒に登校することも変わらない。
ただその時に手をつなぐというオプションがついただけ。
そして昼は自分の手作り弁当を清弥と一緒に食べる。
帰りも委員会があるときは教室ではなく隣の空き教室で待つ。
四六時中彼と一緒にいる。
しかし、それはまるでとても挑戦的だった。
篤貴に見せ付けるかのごとく。
「陽菜、今日は委員会もないから久しぶりに寄り道でもして帰ろうか」
「うん楽しみだな」
「どこに行こうか?」
休み時間、教室で窓際の席で向かい合いながら二人は話していた。
その姿を見ればどう見てもラブラブカップルに間違いない。
清弥に憧れを抱いている女子たちも二人の空気に
指を銜えてみていることしか出来なかった。
清弥はいくつかの場所をあげる。
「映画とか今、面白いのやってるかな?それともカフェで話したりとか?」
「そうだ。この間のWデートのやり直しがしたいな。
この前、あたしが体調悪くして二人に迷惑かけちゃったからそのお詫びも兼ねて」
「いいね。じゃ篤貴に声を掛けておくよ」
「ううん。あそこで話しているみたいだから今から聞いてみよう」
陽菜はそう促すと戸惑っている清弥の手を取って
少し離れた場所でクラスメートと話をしている篤貴に近づいた。
二人の気配に気付いた篤貴はじっとその二人を見る。
篤貴とクラスメートの傍まで行くと陽菜が目配せで清弥に合図を送る。
その合図を見て清弥はまだ戸惑ったまま篤貴に話しかけた。
「あのさ、今日一緒に寄り道して帰らないか?
陽菜がこの間のお詫びしたいって言ってるんだ」
「え?」
「この間のWデートがダメになってしまったからそれのやり直ししたいと思って」
篤貴が清弥の顔を見ると陽菜が口を挟む。
その言葉に視線を陽菜に向けるとにこっと笑顔を見せた。
挑戦的とも取れるその笑顔。
篤貴が好きだといった陽菜が今では清弥の手をぎゅっと握っている。
篤貴は陽菜の考えていることがまったく分からなかった。
「行けるよね?」
「あ、あいつに聞いてみないと分からないな」
「そっか。でも行けなくてもあなただけでも行こう。何かおごらせてほしいな」
「陽菜、そんなに無理強いしたら篤貴にも悪いだろ」
「・・・あいつに聞いておくよ」
よろしくねと去る二人。篤貴は少し身震いした。
彼女の態度が少なくとも変化を見せている。
別れると言った清弥がよりを戻して篤貴の家に来たあの日、
清弥はやっと分かり合えたと篤貴に言った。
それを実行しているだけにはとても思えない。
有無を言わせないあの言動。携帯を取り出し篤貴は莉那にメールを送った。
<今日放課後いけるか?>
休み時間が終わり、授業中に篤貴の携帯は振動した。
莉那からの返信だった。篤貴はそっとその返信を読む。
黒板に板書している教師の目を盗みそっと机の中に携帯を入れて。
<ごめん。今日は無理。また何かあった?>
<いや気にするな。俺が一人で何とかする>
<断ろうか?それにしても急だね。この間は何とかなったけど>
<あいつ変なんだ。今日とても挑戦的で有無を言わせない態度だった>
数回のメール交換で教師が机の周りを回り始めたので
篤貴はメールを途中で止め、黒板の文字をノートに書き写し始める。
そして教師がまた前に戻るとその続きを打ち始めた。
<あいつ変なんだ。今日とても挑戦的で有無を言わせない態度だった。
あの時俺に電話で言ったことはやっぱり嘘だったのかもな。今日は何とか交わす。
お前にそう迷惑ばかりも掛けられないからな>
<そんなことはいいのよ。それより大丈夫?やっぱり断ろうか?>
<いいんだって気にするな。お前だって約束があるだろうし>
<わかった。ごめんね。じゃ今回はパスさせていただく。また報告して>
そのメールで二人のやり取りは終わった。
篤貴は清弥に莉那は無理だということを伝えた。
陽菜はそれでも無理やり篤貴を誘う。
デートに付き合うほど野暮じゃないと言っても聞く耳持たずだった。
結局ショッピングにつき合わされ、
握り合った陽菜と清弥の手を篤貴は黙ってみている事しかできなかった。
「じゃ、今日は篤貴に送ってもらうんだよ」
「うん。清弥も塾頑張ってね」
塾に行く清弥と別れ、篤貴と陽菜は二人になった。
どちらとも言葉を発しようとはしない。ただ駅からの道をとぼとぼと歩くだけだった。
とはいえ、一応清弥から無事に家に連れて帰ってほしいと頼まれた篤貴は口を開き始めた。
丁度篤貴の家がすぐそこだという交差点で。
「・・・家はどこ?」
「・・・別に送ってくれなくても帰れるから」
「清弥に頼まれたから」
「・・・清弥がそんなに大事?あたし、あなたが分からない。
今日あたしたちを見てあなたの顔がすごく苦しそうだった。
自分では気付いていないかもしれないけど」
「そんなこと・・・」
「ないなんて言わせない。あたしはあなたと話したいって思う」
「話すことなんてない」
「あなたにはなくてもあたしにはあるの」
そう言って篤貴の前に回りじっとその目を見る陽菜。
篤貴は瞳を合わせようとはしない。何度合わせようとしても逸らす。
その姿に陽菜は痺れを切らした。
「・・・いい加減あたしを見てよ。見なさいよ。何からそんなに逃げているの?
あたし、自分の言ったことに責任持つから。清弥とはもう本当に別れる。
だから逃げないで。しっかりあたしを見て」
陽菜のその言葉に篤貴はたまらず陽菜を抱きしめた。
そして手を引き、自分の家に連れていく。
古びた階段を上り角の部屋の鍵を開ける。
そしてドアを開け自分が先に中に入り、
陽菜を引っ張り込むとドアをすぐに閉めてそのままドア側に陽菜を押しやった。
視線が絡まる。陽菜の肩をぎゅっと押さえつける篤貴。
「い、痛いよ」
「・・・お前が悪いんだ。全部お前が・・・」
「・・・悪くてもいい。もう自分の気持ちに嘘はつかないって決めたんだから。
あたし、あの日本当に清弥と頑張っていこうって決めた。
それなのにあなたは・・・最初から清弥が別れを告げることを知ってた。
ねえあの時あたしを拒絶した言葉は嘘でしょ?」
陽菜はその状況にひるむことなく、篤貴に問いただす。
もう涙を流していた頃の自分はいない。たとえすべてを失っても自分の気持ちを貫くと決めた。
でも篤貴の気持ちは分からない。
本当に自分のことをただの友達の彼女としか思っていないかもしれない。
だから今日賭けに出た。清弥と一緒にいる姿を見て篤貴がどう反応するか。
そして篤貴は陽菜の期待通りの反応を見せた。
「あたし今日あなたを試した。
だってそうでもしなきゃあなたの本当の気持ちが分からないから。
ガラス越しのキスも電話ももうあたしはあなたしか見えないんだもん。
何度も清弥を好きになろうと思った。キスだってした。だけど無理だった。あたしは・・・」
「・・・もう黙れよ」
篤貴はそう言ってそのまま自分の唇を陽菜の唇に押し付けた。
何度も何度も唇を離してはくっつけるというキス。そして次第に深くなっていくキス。
二人がその心地よさに酔ってしまい夢中で何も考えられなくなってしまった。