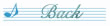Though I should have spent happy time
二人は月の明かりを感じながらゆっくりと歩き始めた。
お互いに言葉は交わさない。
触れるだけのキスをしてしまい、どちらともなく恥ずかしい思いを感じていたから。
陽菜の家から少し歩いたところに小さな公園がある。
滑り台とジャングルジムの2つしか遊具がなく、小さなベンチがあるだけの公園。
二人はゆっくりとベンチに足を進め、そこに座った。
二人とも視線を合わせることなく清弥のほうからゆっくりと口を開いた。
「陽菜・・・」
「・・・ごめんね」
「謝るのは陽菜じゃないよ。俺だよ。俺があんなことしたんだ。俺が悪いんだよ」
「ううん。清弥は悪くない。あたしが悪いの」
陽菜がそういうと清弥は陽菜の両肩をそっと掴んで自分のほうに向けた。
強いまなざし。清弥はゆっくりと大きく首を横に振る。
「俺が悪いんだ。だから自分を責めないで。俺、陽菜に嫌われるようなことをしたんだから。
だから俺を責めてくれればいいんだ。思ってること言ってよ。
俺は許してほしいなんていわないから」
そんなに強く自分を思ってくれているなんて思いもしなかった。
どうして私はこんなにこの人に思われているのだろう。
清弥のまっすぐな瞳が眩しかった。
「・・・清弥はそうやって自分を責めているけどあたしだって非はあるよ。
清弥のこと信用していなかった。信じてあげられなかった。
あたしは・・・清弥をちゃんと見ていなかったんだから。
だから清弥はあたしを責めても自分を責めないで」
「陽菜・・・」
「清弥がそうやって自分を責めるのをあたし、見ているの辛いよ。
あたしが悪いんだから責めないで。お願いだから」
「・・・どうしてそんなこと言うんだ?俺は・・・」
「そんなことじゃないの。あたしはそれを気にしてるわけじゃない。
あたし、清弥のこと・・・」
陽菜はそう言い掛けたときふとさっきの篤貴の言葉を思い出した。
それだけは言うなと声を荒げて言われた言葉。
それにその一言を言ってしまえば清弥を傷つけてしまう。
何度彼を傷つければいいのだろう。
こんなに彼は自分を愛してくれているのに。何も返せない。
唇をぎゅっとかみ締めて陽菜はその言葉を呑んだ。
「・・・ちゃんと信じてあげられなかったから」
「陽菜」
それしか言えなかった。
清弥はぎゅっと陽菜を抱きしめる。その温度が心地いい。
心臓の音が聞こえてくる。それだけ清弥は緊張しているのだろう。
これからこの人をゆっくり時間を掛けて好きになろう。
きっと篤貴のことが忘れられるようになれば彼を誰よりも好きになれるはず。
陽菜はゆっくりと清弥の身体に腕を回した。
そして二人の顔が近づく。
さっきよりもずっと温かくて優しいキスを交わした。
ぎゅっと握られた手。二人はゆっくりと陽菜の家に向けて歩みを進めていた。
他愛のない話をしながら。
「今日はたくさんいろんなことがあったね」
「そうだね。でも俺にとって陽菜とやっと心が通った大事な一日になった気がするよ」
「清弥」
「陽菜は俺に何も言ってくれないだろ?しんどいときも無理して。
今日だって何も言わなかった。本当なら今でも責めてほしいって思ってる。
陽菜は俺を信じられなかったって言うけどあの状況で信じてほしいなんていえるわけないよ。
だから・・・」
清弥の手を離し、ぴたっと足を止める陽菜。
慌てて清弥が陽菜に駆け寄るとじっと清弥を見る。
そして右手の親指と中指をくっつけて清弥のおでこにでこピンをした。
「陽菜?」
「これで許してあげる。だからもうしないでね」
にこっと笑う陽菜。
清弥はためらいなく彼女を抱きしめた。そして陽菜も彼を抱きしめる。
そして手を握りまた歩き始めた。
家の近くまで来ると陽菜はふと思ったことを清弥に聞いてみた。
「清弥、そういえばどうしてうちの前にいたの?」
「え?そ、それは・・・」
「まさかあたしを心配して?」
「・・・まあそうかな」
「いつから?」
「電話する前からだよ」
「電話する前?!じゃあかなりの時間にあそこにいたの?」
「・・・うん」
「清弥・・・」
陽菜がそっと清弥の顔を覗きこむととても赤い顔をしていた。
学年の王子様のこんな顔きっと他の女の子が見れば卒倒するだろう。
いつもにこにこと笑顔を浮かべて優しい表情と言葉で包み込んでくれる。
女の子にとって理想の男の子だろう。
「ありがとう」
「情けないよ。ほんと。自分から別れようって言ったのにさ」
「ううん。嬉しかったよあたし。清弥にそんなに思われてるんだって」
「いいの?俺ともう一度やり直してくれるの?」
「やり直すも何もあたし別れることに同意なんてしてないよ」
「陽菜・・・」
二人は陽菜の家の前まで来ていた。
携帯で時間を確認すれば12時を回っている。
辺りはすっかり暗くなり、家の明かりも消えて街灯と月の明かりしかない。
「じゃ、また明日ね陽菜」
「清弥、今から終電あるの?」
「あ、それなら心配しなくていいよ。家には帰らないからさ」
「え?どうするの?まさか野宿?」
「野宿か。それも面白いね。でも今日は違うよ。篤貴の家に行くんだ」
「え?」
「ここから近いからさ。歩いて5分くらいのアパートにあいつ一人で暮らしてるんだ。
だから今日は泊めてもらう。篤貴に事情も話しているしね。
そしたらあいつ気の済むまで話してこいって言ってくれたんだ。ほんといいやつだよ」
もう遅いから家の人を起こさないようにと促され陽菜は家の中に入った。
清弥から聞いた言葉が何度も響いている。
彼は最初から清弥がここにいることを知っていた。
あの言葉はもしかしたら彼の本心じゃないのかもしれない。
でも今更そんなこと考えちゃいけない。
彼を、清弥を本当に好きになると決めたのだから。
それなのに胸の高鳴りがやまない。
二度も清弥とキスを交わしたはずなのにガラス越しのキスが蘇る。
こんなんじゃダメ。頭を振り、物音を立てないように階段を上り部屋の扉を開けた。
「・・・何が本当なの?」
呟いた一言。
篤貴の言葉は本心?それとも・・・。
清弥と心を通い合わせて幸せな時間を過ごしたはずなのに
篤貴の言葉ばかり考えてしまう。もう遅い。
清弥をちゃんと好きになれたなんて嘘だった。
恋してる相手は佐藤篤貴。陽菜は決めた。
篤貴と話をしようと。
もしそれで清弥と篤貴の両方を失うことになっても仕方ないと覚悟を決めて。