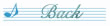Words of farewell and the first kiss with him
陽菜は家に着くとすぐにまた何も言わず自分の部屋に駆け込んだ。
清弥と一緒に帰りながらも心の中は篤貴が支配している。
制服のままベッドに伏せて唇に触れてみた。
たとえ壁があったにせよ誰かと唇を合わせることが初めての陽菜にとって
衝撃的でかつとても激しい思いが駆け巡る。
もし、このまま清弥と付き合っていればいつかは直接唇を合わせることになるだろう。
清弥にもそう言われた。
「陽菜・・・俺、他の女とはさ、遊びでキスできるんだ。
こんなこと言ったら軽蔑されるかもしれないけど・・・
けっこう無理やりされたりとかしてたから慣れた。
だからさっきも・・・。でも俺、陽菜にキスしたいって思う。
本当に自分からキスしたいなんて思える人に出会うなんて思わなかったけど・・・
だから今度はキスするから」
その清弥の言葉には確実に決意が込められていた。
決してもう他の女の子とキスはしない。
望んだ答えが返ってきたはずなのに、どうしてだろうこんなに心が晴れないのは。
それに怖くもなっていた。いつキスされるのだろうと。
ポケットから携帯を出し、おまじないのように篤貴のメモリーを出す。
そのまま指に触れると少しだけ不安が和らいだ。
もし、こんなことを言えば篤貴はなんと言うだろう。
清弥の気持ちに応えてやれというのだろうか。
それとも今度は直接キスをくれるのだろうか。
聞いてみたい。彼がどう思っているのか。彼女がいるのはわかってる。
でもガラス越しにキスをしようといったのは紛れもない篤貴。
自分のことを本当はどう思ってるのだろう。仰向けに向き直り天井に携帯をかざす。
あのキスをどう思ってるの?私のことどう思ってる?
ボタン一つ押せば聞けるはずなのに。聞いてはいけない気がする。
「・・・私のこと・・・」
そう呟いた瞬間、着メロが鳴る。表示された名前は清弥。
大きく深呼吸をして電話に出る。気付くと何故だか正座をしていた。
「もしもし・・・」
「・・・はい」
「ごめん。今、忙しかった?」
「ううん。大丈夫」
「・・・俺のこと嫌いになった?」
「え?」
「声が上ずってるからさ。俺の話聞いてやっぱ無理だって思ったんなら・・・別れてもいいよ」
清弥はいつも突然だった。それだけ陽菜に溺れている。
必死で必死で繋ぎ止めておきたい。だけど陽菜の心はちゃんと手には入ってない。
不安で流されてキスしたといっても過言ではなかった。
「別れたいの?」
「それはこっちが聞いてるんだよ。俺は無理してまで付き合ってほしくはないんだ。
今日の帰りさ、陽菜無理してただろ?やっぱり俺は嫌われたんだなって。
いやもしかしたら最初から好きになんてなってもらえなかったのかもしれないな」
ぐさっと刺さるその言葉。陽菜のすべてを見透かしていた。
清弥と付き合い始めて無理ばかりしていた自分。
本当は篤貴が好きなのに篤貴とのつながりを失いたくないから
ずるずると清弥と付き合っている。
まっすぐな気持ちをぶつけてくれる清弥にこれ以上嘘をつき続けるわけにはいかない。
「清弥・・・」
「・・・ごめんね。陽菜、別れよう」
あの優しい清弥が自分に継げる優しさ。涙が出るのは何故?
篤貴とのつながりがなくなるから?違う。そんなんじゃない。
こんなつぶれそうな清弥の声を聞くだけで胸がぎゅっと締め付けられる。
彼に何をしてあげたのだろう。
こんな風に自分ばかりを責めることばかりをさせて極めつけの言葉まで言わせてしまった。
傷つけることしかしていない。
「じゃ、切るね。今までありがとう」
そう言って電話は切られた。
これでいいの?陽菜は何度も自分に問いかけた。
清弥に自分がしたことは苦しめるだけだった。
確かに他の女とキスをしていた清弥に非がある。
でもそれは自分がいつも心ここにあらずの態度を取っていたことにも原因があるはず。
それなのに、思いつくのは篤貴の顔。陽菜は思い切って彼の携帯に電話を掛けた。
「はい」
「槙原ですけど・・・」
そう言って陽菜は清弥と別れたことを告げた。
何も言わず黙って聞いている篤貴。
そして一通り話しを終えると篤貴はゆっくりと口を開き始めた。
「・・・それで別れたのか?」
「・・・うん。でも・・・これでよかったのかもしれない。私、清弥のこと・・・」
「言うな。それ以上言うな。・・・自分でやったことに責任持てよ。
あんたは清弥の告白を受けたんだ。
キスのことが許せないならあんたはそれを責めれないだろ。俺と・・・。
とりあえず今すぐ清弥に電話して取り消せよ」
優しく慰めてくれるかと思った。それなのに篤貴から出る言葉は責める言葉ばかり。
陽菜の意見なんて聞き入れようともせずにただひたすらに責め続けた。
「あんたなんで清弥の告白受けたんだ?
どうせあいつがかっこいいとか、連れて歩ければとか思ったのかよ?
あんたはそんなんじゃないって思ってたのに・・・失望したな」
「・・・そんなんじゃない!!私は・・・」
私はあなたが好き。だけどもうあなたは手に入らないのなら・・・
そんなこと言っても仕方がない。結局は身代わりでOKしたようなものなんだから。
「なんだよ?」
「・・・どうしてキスしたの?」
「は?!」
「どうして私にキスしたのよ。・・・私はあなたが好きなの」
電話にはもう切れた電子音しか響かない。今更なんて遅かったんだ。
そう。あの時に戻れるなら絶対に告白を受けたりしない。
だけど・・・どう考えても篤貴は自分の思いには応えてくれない・・・友達の好きな人だから。
「・・・キスは対等の立場にするためだ。
それに気にかけたりしてるのはあんたが清弥の好きなやつだから。
俺は友達の好きなやつを好きになったりはしない」
絶望に突き落とされたような気がした。陽菜は携帯を持ったまま窓を開ける。
涙が頬を伝った。もう何も考えたくない。
身を乗り出してこのまま地面にたたきつけられれば気が済むのだろうか。
「陽菜」
その瞬間に聞こえた声。制服姿のままの清弥が家の前に立っていた。
陽菜は窓を閉めて急いで階段を駆け下りた。
そしてドアを開くと清弥にぎゅっと抱きついた。
「清弥!!」
ぎゅっと抱きしめる手に力がこもる。清弥はゆっくりと陽菜の体を抱きしめた。
さっきまでの貫かれた心を優しく包み込んでくれるような抱擁。
彼はとても温かい。自分に別れを告げてまでもやってきてくれた。
この人なら割れてしまった心を元に戻してくれるかもしれない。
「清弥・・・傍にいてほしい」
「いいの?」
こくっと頷く陽菜。ゆっくりと近づいてくる清弥の顔。
思わず目をつぶると二人の唇は重なった。
初めてのキスは涙味の悲しいキスだった。