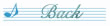A kiss of cheeks with love, a kiss of a lip without love
姉の章乃が部屋から出ていってどれくらい過ぎたのだろう。
時計の針は動いているのに
陽菜は時間が止まっているかのような錯覚に陥った。
自分の部屋の中でさっきの言葉がエコーのように響き渡る。
「その彼のことだけど諦めたほうがいいわ。
絶対に叶わない片思いよ。
彼には友達の彼女と付き合うなんてこときっとできない。
あなたが清弥くんと付き合った時点で
彼の中ではもう異性の対象外にすぎないわ」
自分はどう頑張ってももう異性としては見られない。
ついて回るのは『清弥の彼女』という肩書き。
そんなものなんてほしくない。
でもそれすら失ってしまえばもう篤貴との繋がりはなくなってしまう。
・・・絶対にそれだけは耐えられない。
それならいっそその繋がりでだけでもつながっていたい。
陽菜はそう思った。
「・・・清弥の彼女でいなきゃ」
翌日、陽菜は新しい気持ちで制服のリボンを結ぶ。
決意は変わらない。
それに本当に清弥の傍にいればいつか篤貴を忘れられるかもしれない。
目の前の鏡に写った自分。
もう泣いたりしない。
どんなに好きでも篤貴はそんな風には見てくれない。
この想いはしまうんだ。そう言い聞かせた。
「おはよう。お姉ちゃん」
「・・・ひどい顔ね。目が真っ赤よ。清弥くんには言うことにしたの?」
「・・・ううん。あたし清弥の傍にいる」
「陽菜」
「清弥はあたしのことを好きでいてくれる。その気持ち大切にしなきゃね」
部屋を出ると章乃にすれ違った。
自分の気持ちを笑顔を見せて話すと陽菜はとんとんと階段を下りていった。
章乃は不安になった。
本当に自分の言ったことが伝わったのかと。
自分もとんとんと階段を下りると
さっきの笑顔と変わらない陽菜がおいしそうにトーストにかじりついていた。
「あ、お姉ちゃんも食べなよ。この苺ジャムおいしいよ」
くったくのない表情。
章乃は自分が昔、陽菜の状況を経験したからでからこそ、
自分の可愛い妹が傷ついて涙する姿を見たくなかった。
陽菜はストレートの肩までの髪、華奢な体。
それに大きな瞳と外見にはまったく問題はない。
出来ることなら幸せな恋をしてほしい。
あんな作り物の笑顔でなく、
ほんとに幸せな笑顔を見せてほしいと願っていた。
陽菜は朝食を済ませると一度自分の部屋に入った。
すーっと大きく深呼吸をすると携帯を取り出す。
電話帳の中から昨日登録した篤貴のメモリーを出してまた撫でてみる。
愛しい気持ちが湧き上がった。
叶わなくてもいい。
せめてこうやって彼のメモリーを撫でるだけでも陽菜には十分だった。
部屋の掛け時計を見て時間を確かめると携帯をしまい、階段を下りる。
章乃は先に出ていて母親が洗濯機を回している音が響いていた。
「行ってきます」
母親に言い残し、家を出る。今日はそんなに天気もよくない。
お気に入りのモスグリーンの傘を手にすると駅へと歩き始めた。
ぽつぽつと降り出した雨。
モスグリーンの傘は即座に役に立った。
ばさっと音を立てて傘を広げる。
雨に濡れないようにと買った傘は
陽菜の体をすっぽり包み込めるくらいの大きさだった。
駅に着くと傘をたたみ、定期を改札に入れる。
電車を待つ列の人波の後ろに並ぶと清弥が声を掛けてきた。
「おはよう」
「清弥?!どうしたの?」
いつも清弥との待ち合わせは電車の中。
前から2両目の車両に陽菜の駅から4つ目の駅で乗ってくる。
しかし、今日は陽菜の駅にいた。
ふと辺りから声がするとどうやら清弥のことを言っているようだった。
清弥は高身長と甘いマスクを持ち合わせていて好意を寄せている女子は多いほうだ。
陽菜と付き合ったとはいえ、その人気は衰えることはなかった。
「昨日陽菜が元気なかったから迎えに来たんだ」
「清弥・・・」
笑顔を浮かべてそう言う彼。
どうしてこの人を胸が焦がれるくらい好きになることができないのだろう。
そうすれば素直に彼の隣で笑えるのに、幸せを感じられるのに。
到着した電車に2人は乗りこんだ。
まだ清弥への黄色い声はかすかに耳に聞こえてくる。
しかし当の本人はそんなことにまったく構いはしない。
目の前にいる陽菜ににこにこと笑顔を浮かべている。
罪悪感が襲う。
今日の朝、自分がしたことは彼への裏切り行為。
それでも彼から離れられないのも
篤貴との繋がりを失いたくはないがための手段。
「今日、また委員会があるんだけど・・・」
「・・・待ってるよ」
「でも具合大丈夫?昨日の今日だから無理はしないほうがいいと思うけど」
「大丈夫。それに今日わざわざ迎えにまで来てくれたんだから今度はあたしが待ってるよ」
にこっと笑顔を作ると返ってくるそれ以上の微笑み。
電車の中の仲睦まじい二人はどこから見てもお似合いのカップルに見えた。
電車が学校の最寄駅に着くと二人と同じ制服の生徒達がぞろぞろとホームを歩く。
二人もその波に混ざり改札を抜けた。
「傘、忘れた」
雨は勢いを増していた。
陽菜がモスグリーンの傘を開くと隣で清弥がそう呟いた。
この傘なら二人が入っても大丈夫。
清弥の肩をとんとたたき、傘の中に入ることを促すと
申し訳なさそうに清弥が中に入ってきた。
合い合い傘。付き合っているのだからそんなこと気にしなくてもいい。
160cmの陽菜より15cm高い清弥が傘を持って雨の道を歩きだした。
「この傘大きいでしょう」
「うん。二人入っても平気だもんね」
「あたし雨に濡れたくなくて大きな傘を探してたの。
でも大体デザイン重視の小さな傘ばかりで全然なくて。でも丁度こんな雨の日、
傘も持たずに出かけていたあたしはこの傘に運命的に出会ったの。
見つけてすぐに一目ぼれ」
「そっか。大好きな傘なんだね」
「うん。大好き」
「・・・俺も」
「え?」
そう言って陽菜が清弥に振り向いた瞬間、彼の唇が陽菜の頬を掠めた。
傘の中での小さなキス。
恋人同士なのだから別に許される行為。
清弥は顔を真っ赤に染めて陽菜は目を見開いていた。
でも嫌悪感は感じなかった。
立ち止まった二人をどんどんと人が追い抜いていく。
照れくさそうに言葉を発したのは陽菜のほうだった。
「びっくりした」
「嫌だった?」
「ううん。驚いたけど」
「・・・よかった。やってちょっと失敗したかなとか思ったりしてさ」
やっぱり笑顔で陽菜を見る清弥。
もしかしたら彼のことを少しずつ好きになり始めているのかもしれない。
笑顔を返し、お互いを見て再び歩き出した。
人よりも少し歩調の遅い陽菜に合わせて清弥もゆっくり歩く。
王子様。この形容詞が彼にはとても合っている。
付き合い始めてやっと恋人らしくなった二人だった。
放課後、すっかり雨も止んで誰もいなくなった教室で
清弥の委員会が終わるのを陽菜は待っていた。
そう。あの日もこんな風に雨の止んだ日だった。
篤貴が声を掛けてきたのは。でも、今日はその気配もない。
窓際の椅子に座ってぼんやりと空を見上げると曇り空が広がっていた。
雨は止んだとはいえ、天気は一日悪かった。
教室の後ろの時計の針の音がまた耳に響く。
そのまま机に伏せて陽菜は眠ってしまった。
「ん・・・」
教室の外からざわざわと声が聞こえてきて陽菜は目を覚ました。
時計を見ると30分くらい寝ていた。
そろそろ清弥が帰ってくるだろう。
しかし、どれだけ待っても彼は戻ってこない。
声もだんだんと聞こえなくなり、教室を出てみた。
ちょうど隣の教室から人が出てきたので
委員会が終わったかと聞くと終わったと言われた。
清弥は残って何かをしてるのかもしれない。
陽菜は教室に戻り、
モスグリーンの傘とカバンを持って
委員会のあった教室に行ってみることにした。
ふと教室の前から聞こえる声。
女の子と男の子が話しているみたいだった。
声をよく聞けば清弥の声。
陽菜は聞き耳を立てるのは悪いと思いながらそのまま耳を澄ました。
「好きなの」
「俺、彼女いるから」
「・・・それでも諦められないの」
「・・・悪いけど」
「じゃ、キスしてくれたら諦める」
女の子の言葉に陽菜は耳を疑った。
キス?仮にも清弥は自分と付き合っている。
それに自分達ですらまだ頬のキスしかしていない。
そんなことするはずがない。
陽菜はその場を離れようとした。
「わかった」
確かに聞こえた清弥の言葉。
目の前が真っ暗になる。
そしてその真相を確かめるために陽菜は
開けてはいけない扉を開けてしまった。
陽菜の瞳に映るのはショートカットの女の子と自分の彼氏のキスシーン。
「陽菜!?」
清弥は急いで女の子から離れたが時すでに遅し。
二人のそのシーンを見て口に手を当てて
驚いた表情をしていた陽菜は一目散に走り去った。
そこには陽菜のお気に入りのモスグリーンの傘だけが残っていた。