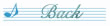I want to come back on that day
授業が終わった。
ほとんど耳には入ってこない授業内容。
ノートもちゃんと取ることができなくて
時計の針の音がやたらと大きく感じる。
それ以外は何も聞こえなくてすべてが
テレビの音を消したときのように陽菜は感じた。
後に待ち受けているものはあまりにも耐え難いものだったから。
このまま何か理由をつけて断ればいい。
頭の中では分かってる。それなのに何もできない。
陽菜は自分を偽り続けることに限界を感じつつあった。
「じゃ行くか。それにしても篤貴の彼女ってどんな子なんだろうな」
「・・・そだね」
「悪いな。待たせた。こいつ・・・彼女。一つ下なんだ」
「はじめまして伊藤莉那です」
教室の前で篤貴と彼女を待っていると二人がやってきた。
篤貴の隣にはかわいい女の子。目がくりくりで身長は低い。
小柄で華奢で見るからに女の子というその彼女に陽菜は目を奪われた。
「今日は誘ってくださってありがとうございます」
にこっと笑う彼女には自分にないものがたくさんある。
そんな風にあたしは可愛く笑えない。
そんな風に女の子らしくなれない。
そんな風に自分の気持ちに正直になれない。
陽菜は自分を心の中で卑下した。
じゃ行くかという声で歩きだす。先導を切るのは篤貴と莉那。
幸せそうに篤貴の腕に自分の腕を絡める莉那の姿が映る。
陽菜は泣きたい気持ちを必死でこらえた。
「俺らもやろうか」
清弥がそう言って陽菜の手を握った。
小さい手だなとくすっと笑いながら。
そうでしょなんて軽く返してみるも陽菜の心は辛くてたまらなかった。
そのまま手をつないで校門を出て行く場所に困ったのでカラオケに行く事になった。
離さないといわんばかりにぎゅっと握られた手。
痛みしか感じない。体中が全部痛みに感じられた。
「あ、あたしちょっと電話してくるね」
カラオケ屋に着いてそれぞれ曲を選び始める。
自分の前では楽しそうに曲を選ぶ篤貴と莉那。
目も当てられないくらいで陽菜は吐き気すら覚えた。
そして軽く理由をつけて外に出た。化粧室に入り、
そこでこらえきれなかった涙を流した。嗚咽を漏らしながら。
どうしてどうしてこんなに辛いんだろう。どうしてこんなに苦しいの。
どうして自分は清弥と付き合ってしまったのだろう。
絶対に思ってはいけない後悔。
それすら頭に浮かぶほど自分では
どうすることもできない痛みが襲い掛かっていた。
「気分大丈夫?」
「あ、うん」
「槙原さんさ、溜めすぎなんじゃない?
言いたいこととかはっきり清弥に言ったほうがいいよ」
「え?」
「顔に出てるよ。あいつ何にも言わないだろうけど気にしてると思うからさ」
化粧室を出るとそこに篤貴が立っていた。
自分のことを心配してくれたのだろうか。そんな錯覚に陥る。
でも篤貴から出た言葉はやはり清弥のこと。
当然だろう清弥は陽菜の彼氏なのだから。
もう今は清弥のことでもいい。篤貴の声に酔っていたい。そう思った。
「そ、そんなことないよ」
「清弥のこと大事にしてやってくれよな。
そんなんじゃあいつかわいそうだから」
「う、ん」
人の涙は枯れることがないのだろうか。
さっきあれだけ流れたはずの涙がまだ流れるような気がする。
篤貴の声に酔っていたいと思った瞬間の突き放す言葉。
篤貴はもう自分を清弥の彼女としてしか見てくれない。
「うん。ごめん。清弥にも謝る」
「おう」
「あたしもうちょっとここにいるよ。今日そんなに気分よくないのに無理しちゃって」
「なら俺もここにいる」
「いいよ。大丈夫。それに莉那ちゃんが妬いちゃうよ」
「ああ。あいつはそんなことで怒ったりしないし、清弥の彼女だってわかってるから」
優しくしないで、突き放さないで、
誰かを好きにならないで、あいつなんて言わないで。
そんな感情が全部一気に押し寄せてくる。
それなのに篤貴は戻ってくれない。
泣く事すらも許されない。神様これは嘘をついた罰ですか・・・。
「寛大なんだね。でもほんと今は一人になりたいの。だから部屋に戻って」
「・・・わかった」
そう言って篤貴は部屋に戻っていった。もう限界。もう無理。
荷物なんてどうでもいい。お金だって後から払えばいい。
陽菜は唯一制服のポケットに入った携帯だけを持ってカラオケ屋を飛び出した。
気付けば流れている冷たいもの。
それでもいい。もうどこかに行きたい。
あんな場面を見たくない。あんな言葉を聞きたくない。
陽菜はただ走り続けた。
どれくらい走ったのだろう。息も切れ切れで涙と汗が混じっていた。
携帯が震える。画面には清弥の名前。
電話になんて出れるわけがない。
気がつけば落ち込んだときに一人でくる公園にきていた。
その電話に気付かない振りをして陽菜はベンチに腰を下ろした。
ぎゅっと携帯を握り締める。
その上にぽたぽた落ちる雫。
それでも携帯は震え続けていた。
最初は目が合うだけ。ただそれだけだった。
それなのにそれが当たり前になって、
いつしか待っている自分がいて・・・でも急に合わせてくれなくなった瞳。
距離は近くなったけれど確実に心は遠くなった。
きっと瞳を合わせたときからもう陽菜は篤貴に恋をしていたのかもしれない。
「バカみたい・・・あたし・・・」
暗くなってきた夕空にぽつりと呟く。
涙は一向に枯れない。これからどうすればいいのだろう。
いっそ携帯を壊して学校を辞めればもう二人に会わなくて済むだろうか。
陽菜の脳裏にはそんなことまでがよぎっていた。
そんなときだった。
少し向こうから誰かが走ってくるような気配を感じる。
じっと目を凝らしてみてみるとそれは制服を着た少年。いや篤貴だった。
「な、なんで?」
「それはこっちのセリフだろ。
先に部屋帰っとけっていう割りにいつまで経っても戻ってこないし見に行ったらいない。
店員に聞いたら帰ったとか言うから俺ら探し回ったんだぜ」
「・・・ごめんなさい」
「だからさっき言っただろ?溜め込みすぎだって。ちゃんと思ったこと言わないと伝わらないぞ。
清弥に電話するからな」
「待って。お願い電話しないで」
「・・・あんまりうまくいってないのか?」
篤貴の問いかけに陽菜は首を振った。
そのとき篤貴は陽菜の頬に光るものを見つけた。泣いていた。
そう思った篤貴はわかったと携帯をポケットにしまう。
そして陽菜の隣に座った。
「俺でよかったら相談に乗るけど」
「・・・ううん。大丈夫。今日はほんとに気分が悪かったの。だから気にしないで。
清弥とうまくいってないとかそんなんじゃないから」
篤貴が自分を探しだしてくれたこと。
それが陽菜にとって嬉しくもあり、苦しくもあった。
どうしてこの人は自分の気持ちをかき乱すようなことばかりしてくるのだろう。
優しく期待させたり突き放したり。
それがとても辛かった。
「そうか」
「うん。だからもう帰っていいよ。あたしなら大丈夫。
今日はせっかくの・・・Wデート壊しちゃってごめんね」
「・・・なんでそんなに無理するんだ?どうしてしんどいならしんどいって言わない?」
「・・・最初は大丈夫だと思ったの。
でも・・・途中でしんどくなっちゃって・・・でもここでゆっくりしてたら落ち着いた。
だから帰って。あたしももう少ししたら帰るから」
もうこれ以上何も言わないで。聞かないで。黙って帰って。
そうしてくれれば思いきり泣くことができる。
それなのに篤貴は立ち上がろうとはしなかった。
「それでいいのか?そんなこと望んでるんじゃないだろ?ほんとは傍にいてほしいんだろ?」
「・・・な、何言ってるの。あたしそんなこと・・・」
「お前俺の目見てないだろ。上っ面の言葉だけ並べても信用できない」
「ぜ、全然そんなことない」
「だったら俺の目見て言ってみろよ。さっさと帰ってくださいって」
篤貴はそう言うと陽菜に体を向けた。
陽菜は視線を痛いくらいに感じるも篤貴と瞳を合わせることが出来なかった。
篤貴の瞳を見れば嘘をつくことなんて出来ない。
本当は傍にいてほしい。そう言ってしまうのは分かっている。
だから瞳を合わせることができなかった。
「見れないんだろ?俺の目。嘘ついてるもんな」
「・・・・」
「槙原さん、もう少し素直になったほうがいいよ。でないと潰れちゃうぜ」
「・・・」
陽菜は言葉を返すことが出来なかった。
どうしてこの人はこんなにも自分のことが分かるのだろう。
もし、もし時を戻すことが出来るのなら清弥の告白してくれた日に戻りたい。
陽菜はいつの間にか出ていた月を見上げながらそう思った。