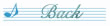It is already late
「好きなんだ」
「・・・あたしのこと?」
「うん。付き合ってほしい」
「・・・・」
「やっぱりダメかな?」
「・・・ううん。ダメじゃないよ。あたしでよければ」
夏休みが終わり新学期が始まって、学校に来なかった
佐藤篤貴が学校に来るようになった。
別段変わった様子もなく、陽菜は安心した。
いろいろうわさが飛び交っていたが
やっぱりそれはうわさにすぎなかったからだった。
しかし、ただ一つ変わったことがある。
それは篤貴が前のように瞳を合わせなくなったこと。
どれだけ視線を送っても見向きもしない。
誰にも話せない違和感を感じていたある日の出来事。
陽菜は篤貴の親友、都築清弥に告白された。
そして陽菜はその告白を受けたのだった。
「篤貴おはよう」
「おはよう」
「おう」
付き合い始めて二人は一緒に登校するようになっていた。
他愛ない話をしながら校門をくぐると篤貴が下駄箱で靴を履き替えていた。
清弥はポンと篤貴の肩をたたき挨拶をする。釣られて陽菜も篤貴に挨拶をした。
篤貴はそっけない挨拶を一言交わすと一人先に教室に向かい歩き始めた。
「あいつそっけなくてごめんな」
「う、ううん。大丈夫」
清弥と付き合い始めて陽菜は清弥を好きになり始めてはいた。
彼の優しさに触れ、そして愛情を感じ、
自分もこの人を好きなんだろうと思った。
携帯が鳴るとドキドキしたり、メールが来ると嬉しかったり、
ちゃんと恋をしているんだと実感していた。
それなのに、すべての歯車はあの日、また狂い始めた。
「清弥待ってんの?」
「・・・?!」
清弥と付き合い始めて間もない頃、
陽菜は一人教室で清弥の委員会が終わるのを待っていた。
清弥の席に座り、
彼女なんだなと実感しながらぼんやりと窓の外の景色を見ていた。
そんなときガラっと扉の開く音がする。
ふと視線をやるとそこには篤貴が立っていた。
篤貴と清弥が親友だということは清弥から聞いていた。
しかし、陽菜が清弥と付き合うようになってから
篤貴は清弥と距離を置いていた。
というよりは避けるようになっていた。
「あ、うん」
「そっか。あいついい奴だろ?」
「う、うん」
「優しいし正義感あるしさ、それに俺とは正反対だしな」
「そ、そうかな?」
篤貴が歩いて陽菜の近くに来る。初めて交わす会話。
胸の高鳴りが止まらないことが分かる。
篤貴の切れ長の瞳が陽菜の目に映る。
あのときから初めて瞳をあわせた瞬間。
目を離したくない。
「槙原さんって清弥とお似合いだと思うよ。あいつのことよろしくな」
くすっと笑って言う篤貴が陽菜の中の何かをはじけさせた。
でも篤貴はそれだけ言うと陽菜から離れて教室を出て行った。
陽菜はしばらく呆然としていた。
初めて間近で聞いた彼の声。
低いながらも聞きやすい。久しぶりにあわせた瞳。
そして初めて呼ばれた名前。
篤貴が自分の中のすべてを犯しているかのような錯覚に陥った。
でも彼の言った言葉は清弥をよろしく。自分にはもう何もできない。
行き場のない思いが駆け巡った。気付けば流れている一雫。
清弥には見せられないと陽菜はそれを拭った。
もし、あの時声を掛けられなければ篤貴よりも清弥を好きになれた。
それなのに、最初はただ瞳をあわせていただけなのに、
陽菜は自分が思っている以上に篤貴を好きなことに気付いた。
「今日放課後寄り道しよっか」
「え?あ、うん。いいね。どこに行こう?楽しみ」
清弥に声を掛けられ、陽菜は我に返った。
それまでただ去り行く篤貴の背中をじっと見つめていた。
それに気付かれてはいけないと陽菜は精一杯を装う。
ちゃんと笑えてるよね。あたし大丈夫だよね。
心の中で自問自答しながら清弥を見る。
清弥は笑顔を返してくれた。
クラス委員をやっていて真面目で誠実。それにとても優しい。
温かい心を持っている清弥。早く篤貴のことは忘れよう。
彼のためにも。陽菜はそう思った。
「そうだ。今日篤貴も誘ってみようか?」
「え?」
「やっぱり俺にしてみれば親友と彼女が
仲良くなってくれたらいいなって思うんだけど」
「あ、あたしそんなに話したことないし・・・」
「だからいい機会だろ?篤貴に聞いてみるね」
教室までの道のりで突然清弥がそんなことを言う。
陽菜は氷付きそうになった。
篤貴にはあまり関わりたくない。
それは決して拒否ではない。
会えば会うほど深くなっていく自分の気持ちに
歯止めが掛けられないのが分かる。
清弥と二人でいれば正直、彼に惹かれていくし、
篤貴のことも考えないで済む。
もし3人なんかでいれば
確実に篤貴を意識するのは目に見えていた。
それなのに・・・どうしてこんなに醜いのだろう。
「うん。わかった」
陽菜はそれでも篤貴に会いたかった。
あの瞳にもう一度自分を写してほしい。
自分だけを見てほしい。そんなことできるわけないのに。
それなのにこんなにも篤貴が好きでたまらない。
嘘をついていることが苦しくて仕方なかった。
「今日行けるって。篤貴。いやーWデートだね」
昼休み、陽菜は清弥と二人で空き教室にいた。
陽菜が作ってきたお弁当を広げて二人で食べていた。
卵焼きは甘い味付けよりも
辛いほうが好きだという清弥のために塩を入れて作る。
自分の分は砂糖を入れて。
それを口にすると幸せな気分になれるからと
わざわざ陽菜は味付けを変えて作っていた。
そしてその卵焼きを口にしようとした瞬間、清弥から出た言葉。Wデート。
そうそれは決して3人では成り立たない。もう一人いる。
そしてそれは紛れもない女の子を意味する言葉。
「あいつも彼女できたんだ。いや、どんな子か楽しみだな」
清弥の言葉が胸に突き刺さる。
篤貴に彼女がいる。
その言葉が大好きな卵焼きにも
手が浸けられないくらいに陽菜を苦しめた。
今までそんなこと思ったこともなかった。
篤貴はあまり女の子とは会話をしていない。
いつも話しているのは男子。だからこそ彼女なんていない。
そうどこかで決め付けてた。
でもそれはただの陽菜の勝手な思い込み。
もしかして彼女ができたから
もう自分とは瞳を合わさなくなったのかもしれない。
だとするともうこの想いはしまっておかなければいけない。
「そ、そうなんだ」
「そうらしい。俺ビックリしたよ。てっきり篤貴は・・・」
「え?」
「いやなんでもない。
なんかさあまだ付き合い始めたばかりらしいんだけど
ベタ惚れみたいなんだ。さっきも彼女の話してたしさ」
もうやめて。聞きたくない。
出来る事なら耳をふさぎたい。
そう思うのにもそれは出来ない。
なぜなら自分は清弥の彼女だから。泣いちゃいけない。笑わないと。
そう陽菜は自分に言い聞かせた。
「そ、そうなんだ。じゃ清弥もあたしにベタ惚れしてね」
「俺はもう陽菜にベタ惚れだよ」
そう言って清弥が陽菜の後ろから抱きつく。
陽菜は笑いながら涙を流した。