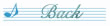The last gentleness of a princee
不思議な運命の巡り合わせだった。
もう会うこともないと思った二人が瞳を合わせ、心を通わせたのだから。
陽菜は清弥と話をしなければいけないと覚悟を決めた。
どんなに清弥が自分を思ってくれたとしてもそれに応えることはできない。
携帯を取り出し、メールを送り始める。話したいことがあると一言だけ。
「メール送ったのか?」
「うん。もうあたしにはあなたじゃなきゃ無理だもの。清弥にはちゃんと話すわ」
「俺も行くよ。俺にも責任はある」
「あなたに何も責任なんてないわ。あたしが悪いの。あたしが・・・」
自分さえしっかりしていれば、清弥を振り回すことなんてしなかったのに。
陽菜は自分を責めた。それに気づいたのか篤貴はぎゅっと背中から陽菜を抱きしめた。
「あんただけが悪いわけじゃない。俺だって清弥を傷つけた。あんた以上かもしれない。
だから自分だけが悪いなんて思う必要はないんだ」
一方清弥は塾になどは行ってなかった。
塾の近くの小さな公園の街灯が照らすベンチに座り何時間も時間をつぶしていた。
そして携帯がメールを受信した。
時刻はもう9時。塾を終えて帰る時間ということもあったのでそっと受信メールを目にする。
彼女からのメールは絵文字はおろか顔文字すら入っていない。
ただ一言話したいことがあるということだけ。
清弥は気づいていた。自分がもう陽菜の瞳には映っていないということに。
いや、最初から自分は彼女の瞳になんて映っていなかった。パタンと携帯を閉じ、瞳を閉じた。
目に浮かぶのは大好きな彼女。それなのにどうして涙が出てくるのだろう。
温和で優しくて頼まれたら断ることもできない王子様が初めて自分から好きになった女の子。
それなのに彼女はいつも自分を見てくれてはいなかった。
「・・・陽菜」
清弥は今までの思いを清算するかのように小さな声で彼女の名前を呟くと
大きく深呼吸して立ち上がった。そして携帯を開き、彼女にメールを送る。
今から会いに行くと。
初めて好きになった女の子との別れ。
辛いけれど彼女が幸せになってくれるのならそれを受け止めよう。
陽菜と清弥はあの公園で待ち合わせをした。そう二人がキスを交わしたあの場所。
清弥がそこに着くと陽菜と篤貴が二人でベンチに座っていた。
二人が立ち上がると清弥は平静を装って二人に近づいた。
「メール見てすぐに来たんだ。ちょうど塾も終わったところだったからさ」
「清弥・・・話があるの」
「うん。どうしたの?」
清弥が笑顔で自分を見てる。そんな優しい笑顔の人に別れてくださいなんて
どうやって言えばいいのだろう。陽菜は口をつぐんでしまった。
こんなに優しい人なのに、どうしてこの人じゃだめなんだろう。
「陽菜?」
「俺から話す」
何も言えない陽菜の肩を篤貴がそっとたたいた。
しかし、清弥はキッと篤貴をにらみつけた。
「俺は篤貴から話があるって言われてきたんじゃない。陽菜から話があるって言われたから
来たんだ。悪いけどお前は外してくれないか。今は俺たち二人の問題なんだ。
お前の話は後から聞くから」
初めて口調を強めた清弥に対して篤貴は驚いた。
しかし、ただ頷いて陽菜の肩をもう一度たたき、そっとその場から離れた。
清弥はもう何を言われるのかをわかっている。
陽菜はその清弥の言葉を聞いてそれを確信した。
だからこそ自分の口から伝えなくてはいけない。
たとえそれがこの優しい王子様を傷つけることになったとしても。
「・・・清弥ごめんね」
「何が?とりあえず座ろうか。何か飲み物でもいる?」
陽菜の横に立ち、ベンチに座るように促す。
さらにまだ飲み物まで買ってこようかという気遣いまで見せる清弥。
陽菜は立ち上がろうとした清弥の服のすそを掴んだ。
「話聞いてくれる?」
「・・・うん」
月明かりが二人を照らし、陽菜は一つずつ言葉を頭の中で選びながら口を開き始めた。
「あのね・・・清弥のこと嫌いになったわけじゃないの」
「うん」
「でもね、清弥とこれ以上付き合うのは無理」
「・・・うん」
「清弥はすごく優しくてかっこよくて王子様みたいで本当にそんな人と付き合えてうれしかった。
みんなからすごく羨ましがられて自分でも信じられなかった」
「そんなに俺はすごい人間じゃないよ」
「ううん。本当に素敵な人だと思うの。女の子の理想の王子様だもの」
「でも陽菜にはそれがうっとおしかった?」
「違う。違うのそんなんじゃない。嬉しかった。
自分が本当に女の子扱いされているって実感できたんだもん」
「そっか」
「でもね、でもそれ以上に大きな気持ちができたの。いつもその人のことばかり考えたり、
その人とずっと一緒にいたいっていう大きなものがあたしを占めるようになった。
いけないことだって何度も何度もあきらめようとしたんだけど、
どうしてもそれが出来なかった。・・・悪いのは全部あたしなの。だから・・・だから・・・」
「陽菜・・・お願いがあるんだ」
「お願い?」
「最後でいいから俺を君の瞳に映してくれないか?瞳を合わせてほしい」
清弥はそう言って両手を陽菜の肩の上に置いた。向きを変えて見つめあうようにして。
お互いの瞳の中にお互いを映す。今、しっかりと清弥の姿が陽菜の瞳に映った。
その瞳が雫を落とす。陽菜が思わず声をかけようとするもそれをさせない清弥。
が止まったかのように見つめあってそして清弥から視線を逸らし、肩から手をそっと離した。
「・・・ありがとう。さ、もう行っていいよ。こんな惨めな俺をいつまでも見せるわけにいかない」
陽菜に背を向けてそう言う清弥。しかし陽菜はそこを動けなかった。
清弥の涙は自分のせい。このまま彼を置いて自分だけ行くわけにはいかない。
しかし、動こうとしない陽菜に清弥はこう言い放った。
「いつまでいるつもりだよ?まったく目障りな女だな。さっさと行けよ」
「清弥?」
「お前の顔なんかいつまでも見たいわけじゃねえんだよ。早く去れよ」
いつもの清弥とはとても違う口調だが陽菜はその言葉に愛を感じた。そして立ち上がる。
もう彼を傷つけたりはしない。彼が望むまで絶対に自分からは近寄らない。
そして彼が素敵な恋をするようにとそう心に誓って・・・
「清弥・・・ありがとう」
そう言って走って公園を後にした。
王子様の初めての失恋はとても涙なくては語れない。
けどきっと次の恋はおとぎ話のような素敵な恋をしよう清弥はそう思った。
そしてそのために自分の親友との最後の決着をつけなくてはいけないと心に誓った。