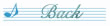春、出会いや別れの時期。
俺、進藤剛にとって卒業なんて言葉はもういつのことかわからない。
社会に出てもう3年。戸惑いばかりの仕事も慣れて営業成績も悪くない。
でも刺激のない毎日にうんざりしていた。仕事と家の往復ばかり。
大学時代に付き合ってた女とも別れて早2年。
彼女もいなくて退屈な日々を送っていた。
そんなときに入ってきた新入社員。男ばかりの職場。
今年こそはかわいい女性新入社員が入ってくるんじゃないかと期待していたが、
その期待はやはり覆され俺の部署に入ってきたのは男ばかりが3人。
「よろしくお願いします」
不安と期待に輝く瞳。俺もそんな目をして希望に満ち溢れて入社したな。
なんてふと昔の自分を見ているようだった。
俺の専属の後輩はつい最近大学を卒業したばかりの安西賢。
身長は俺よりも低い。
自慢じゃないが俺の身長は178cmだから俺より高いやつはこの会社にはいない。
まあ安西の身長は170cmくらいだろう。顔はまあ平均して普通。
うまくやっていけるだろうと思っていた。
「進藤さんは彼女とかいないんですか?」
専属の後輩ができたのは初めてということもあって俺は安西を初日から飲みに誘った。
庶民的な居酒屋で営業のノウハウを教えてやろうと思ったのにやっぱり数日前までは学生。
ついついプライベートの話になってしまった。
安西はどうやらけっこう酒がいけるみたいでビールを軽くジョッキに2杯は煽っている。
酔い始めたのか初対面の先輩にいきなり女性関係を聞くなんてまさにコンパ慣れしているな。
「俺?俺はいないな。仕事が忙しいしな。お前はいるのか?」
ついつい仕事のせいにしながらこいつに質問を投げ返す。
すると安西は少し困ったようなでも照れたような表情をして自分の携帯を取り出した。
彼女の写メでも見せてくるのかと思ったら一通のメールを見せてきた。
<メアド教えてくれてありがとう。卒業したけどこれからもよろしくね(o^o^o)佐藤梨緒>
携帯の画面に映ったそのメール、文面から見て安西の大学の友達のようだ。
しかし、なぜ安西はこのメールを俺に見せてきたのだろう。
すっと携帯を閉じて自分のポケットに戻すと安西は口を開いた。
「大学の友達でまあケンカ友達みたいなやつだったんですけど、
卒業間近になって急に気まずくなったりこうやってメール聞いてきたりしたんですよ。」
「それって・・・彼女お前のことが好きなんじゃないのか?」
「・・・どうなんでしょうね」
「どうなんでしょうってそれ以外考えられないだろうが」
安西の話からして明らかに彼女は安西に好意を抱いているに違いない。
だが、安西の様子からすると彼女の気持ちに応えるつもりはないように見える。
「お前はこの子の気持ちに応えるつもりはないのか?」
「わからないですね」
「好きじゃないんだろ?」
「それもよくわからないですね。あんまりそういうの慣れてないんで」
さっきはコンパ慣れしてるように思ったが
どうやらこいつそんなに女性経験がないのかもしれない。
俺は安西にもう一度メールを見せてほしいと言った。
「どうぞ。俺、ちょっとトイレ行ってきますから」
携帯を俺に差し出し、安西は席を立った。
俺はもう一度じっくりとそのメールを読んだ。
久しぶりに見た顔文字。
俺に入るメールなんて会社の用件とか
大学時代の野郎からの飲みメールくらいだからな。
ふと・・・魔が差した。俺は気づけば返信ボタンを押していた。
<俺、メアド変えたから変更しといて・・・>
その文面と自分のメールアドレスを打って一気に送信ボタンを押した。
そして安西のメールから彼女のメールを削除した。
幸いだったのが俺と安西の携帯が同じ機種だったということだった。
「悪い。間違ってメール消しちまった」
「え?あ、そうなんですか」
席に戻ってきた安西にそう告げると少し寂しそうな顔をして見せたが
それ以上メールのことについては何も言わなかった。
そしてそのまま飲み続け、俺は何もなかったかのように
最初の目的だった営業のノウハウを安西に話した。
<メアド変えるつもりだったの?よかった聞いておいて☆
そういや今日初出勤だったんだよね?
どうだった?先輩とかと仲良くやっていけそう?(o^-^o)>
安西と別れた帰り道俺の携帯がメール受信を知らせた。
開いてみると新着メールの文字。
そのメールはさっきの彼女。佐藤梨緒からのものだった。
俺は返信ボタンを押して安西になりすまし、メールの文章を打ち始めた。
<社会人になったからな(笑)ああ。まあ気が合いそうな先輩の下で働くことになった>
顔文字や俺のことをさりげにアピろうかとも思ったけれど
まずはこんな感じで様子を見てみよう。
俺はそんな風に思いながら送信ボタンを押した。
街灯の灯が送信完了を知らせる。
俺はこのときまだ自分がやったことの間違いに気づいてはいなかった。
それよりも久しぶりに見る顔文字メールに心を躍らせていた。
あれから一ヶ月が過ぎた。
佐藤梨緒とのメールはけっこう頻繁でお互いの仕事のことを毎日報告している。
安西はあれから普通に仕事をこなし、
営業にも向いているような感じに思えたそんな時だった。
「進藤先輩、今日相談したいことがあるんですけどいいですか?」
安西が深刻な顔をして俺にそう言ってきた。営業でヘマをしたわけでもない。
むしろ順調にいっている。プライベートのことだろうか。
俺はもうその頃、自分が安西になって佐藤梨緒とメールしていることなどすっかり忘れていた。
佐藤梨緒とのメールは俺の日課になっていたからだ。
佐藤梨緒とのメールは俺の日課になっていたからだ。
「・・・あいつからメール来ないんです」
初日に飲んだ居酒屋で安西はビールのジョッキも手に取らず下を向いて口を開いた。
俺は思わず飲んでいたジョッキから口を離して目を見開いた。
「確かに俺がメールを返していないからかもしれないけど
あんなメール今更返信するわけにもいかないし、
それに俺からメールするって言ったってどんな風に送っていいのかわからないんです」
安西はそう言ってビールの隣に置いていた水を一気に飲み干した。
もしかして安西はやっぱり佐藤梨緒のことが好きなんじゃないか。
俺の中でそんな考えが浮かんだ。
ここで先輩ならメールの文章を一緒に考えて送ってやるのが普通だろう。
だが、もう安西賢と佐藤梨緒は毎日メールのやり取りをしている事実がある。
そうたとえそれが本物の安西賢ではなくても・・・。
「安西、お前はその彼女と付き合うつもりなのか?
そんなつもりもないのならメールなんてする必要はない。
そんなことをして彼女に期待を持たせてもかわいそうだろう。
そんなに気になるのならもうその彼女のメアドなんて消してしまえ」
自分でも恐ろしいくらい冷たい言葉が口から出た。
安西は目を丸くして俺の顔を見たが、そっと携帯を取り出した。
そうだ、お前の携帯から佐藤梨緒のメアドを消してしまえば
俺はバレることなく彼女とメールのやり取りができる。
最初は顔文字なんて使いもしなかったが
最近になってはその顔文字も少しくらい使うようになった。
彼女から来るメールがすごく楽しみなんだ。
この楽しみを俺は奪われるわけにはいかない。
「・・・消します」
聞こえるか聞こえないかの声で安西はそっと携帯の削除のところでボタンを押した。
そして俺に携帯を見せてくる。画面上には削除しましたの文字が走っていた。
俺は安西に飲め。とジョッキを渡した。あいつはそのジョッキを一気に飲み干した。
<そうそう卒業式の写真ができたんだ☆
だから近いうちに渡したいんだけど会える日とかないかな?
やっぱ仕事始まったばかりだから無理?o(>_<)o>
それから数日後、佐藤梨緒からそんなメールが来た。
正直俺も彼女に会いたいと思っていた。
顔も知らない相手とのメール交換。
さすがに安西に彼女のことを聞くわけにもいかないから
俺が知っている彼女はメールでの彼女だけ。
しかし、会うとは言っても俺は安西じゃない。どうすればいいだろう。
<おお〜いいな。じゃどうしようか?3日の夜ならなんとか行けると思う。
待ち合わせは白木駅の改札に7時でいい?>
<ほんとに?!(≧▽≦)やった★☆じゃ楽しみにしてるね♪>
思い切って約束を取り付けるメールを送ると彼女からすぐにメールが返ってきた。
そんなに喜んでくれるなんてうれしい。
でも彼女が会いたがっているのは安西なんだよな。
そして約束の日の朝、俺は彼女に一通のメールを送った。
<今日どうしても無理になったんだ(T_T)悪い!!
でも俺の先輩が代わりに行ってくれるってことになったから>
<え?そうなんだ(;_;)じゃまた日を改めようか?>
<いやいや俺の先輩いい人だからさ>
<でも・・・そんな知らない人に写真とか渡したくないし・・・またにしよ♪>
知らない人という言葉がけっこうグサっときたけれど
こんなことでひるんでいるわけにいかない。
俺は文章を一生懸命考えながら彼女に返信した。
<頼む。もう先輩かなり乗り気だから行ってやってくれないか?>
<わかった>
7時に白木駅。俺は待ち合わせ場所に着いた。
今日のために新調したネクタイ。なんだか胸がドキドキする。
どの子が佐藤梨緒なんだろう。
そこには数人の女の子がいる。
ちらほらと辺りを見渡していると
ミントグリーンのトップスに白のスカートの女の子が俺に近づいてきた。
「進藤さんですか?」
「・・・佐藤さん?」
「はい。今日はわざわざありがとうございます」
小さくってかわいらしい子だった。メールの文章どおりの。
彼女はごそごそとかばんの中から封筒を取り出し、俺に差し出した。
キャラクターのかわいい封筒だった。
「それ卒業式の写真なんで彼に渡してください。じゃ失礼します」
それだけ言うと彼女はくるっと背を向け、歩きだそうとした。このまま帰すわけにはいかない。
たくさん話したいことがあるのに。俺は彼女の腕を取って歩みを止めた。
たくさん話したいことがあるのに。俺は彼女の腕を取って歩みを止めた。
「どうかしましたか?」
「せっかくだからご飯でも一緒しませんか?」
「え?でも・・・」
「帰っても一人で飯食わなきゃいけないんだ。だから一緒してくれないかな?」
彼女は少し渋っていたがわかりましたと食事を一緒にしてくれることになった。
だが心なしか彼女の表情は浮かなかった。
大学のときに彼女とよく行ったイタリアンの店に彼女を連れていく。
女の子ならこの店気に入ってくれるだろう。
だが彼女はメニューを見てもずっと下を向いている。
仕方がないので無難なカルボナーラとミートソースのパスタを注文することにした。
「俺、安西くんの先輩で進藤剛っていいます」
「・・・佐藤梨緒です」
「あ、佐藤さんは安西くんと同じ大学だったんだよね?」
「はい。ケンカ友達でした」
「大学時代の安西くんってどんな子だったの?」
「え?子供っぽかったですよ。好きな子にすらまともにアプローチできない」
好きな子?安西に好きな子がいたなんて。
じゃどっちにしても彼女は報われることはなかったんだ。
俺にも春到来のチャンスがきたのかもしれない。
このまま安西の話ばかりしていたくもないと思った俺は
彼女のことをもっと知りたいと思って話題を変えることにした。
「佐藤さん・・・梨緒ちゃんでいい?梨緒ちゃんは今何の仕事してるの?」
メールで聞いて知っていることなのに知らないふりをして聞いてみる。
確か彼女は中小企業の受付をやっているといっていた。
しかし、彼女から出た言葉は予想を覆す言葉だった。
「私・・・まだ就職決まってないんです。就職浪人していて今も就職活動しているんです」
「え?」
「恥ずかしくて彼には中小企業の受付なんて嘘ついちゃってるんですけど・・・」
「そうだったんだ」
「・・・彼、私に会うのが嫌だったんですよね?」
注文したカルボナーラとミートソースのパスタがテーブルに並び、
彼女がカルボナーラ。俺がミートソースだと決め、
食べ始めようとすると彼女がそう口に出した。
そうか。彼女の元気がなかったのは安西がここに来なかったからか。
でもそれは仕方ない。安西はここに来ることすら知らないのだから。
「梨緒ちゃんは安西が好きなんだ?」
彼女は黙って頷いた。わかっていたこととはいえ、結構つらい。
そのとき俺はもう彼女に恋をしているんだと思った。
「最初はケンカ友達で全然なんとも思ってなかったんですけど、
卒業間近になってこのまま終わってしまうのが嫌だと思ったんです。
もっと話したい、繋がっていたいって」
「・・・そっか」
「メール聞いて嫌がられたらどうしようとか思ったんですけど
彼、すごくメール返してくれて・・・もしかしたらって思ってたんですけど
やっぱり彼は好きな子がいるんだなって改めて思いました。
だから今日も来てくれなかったんだなって」
「そんなこと・・・」
そんなことないなんて俺の口からは言えなかった。
実際安西はメールを返すことにも戸惑っていたくらいだ。
確かに彼女からメールが来ないことを気にしていたけれども
好きな子がいるんだから彼女に希望はない。
目の前で震えて今にも泣き出しそうな彼女を俺は抱きしめたかった。
「いいですよ。無理して気遣っていただかなくても・・・あれ?メールが入ってる」
「え?」
「ちょっとすいません」
彼女はそう言って携帯を開いた。
顔色が変わったように思えたが俺は目の前にある冷めたパスタを口に入れた。
「どういうこと?」
「どうしたの?」
「いえ、なんかメール来たんですけど・・・」
見てもいい?と俺は彼女から携帯を受け取り画面に目をやった。
<久しぶり。最近どうしてるんだ?メールたまには送ってこいよ>
そのメールは安西からのものだった。しかし、彼女はそれに気づいていない。
今、このままこのメールを間違ったことにして消してしまえば・・・いや、待てよ。
安西は彼女のメアドを俺の目の前で消したはずだ。
じゃこれはきっと違うやつのメールかもしれない。
「返してみれば?誰かわからないならどなたですかって?」
俺は笑顔で彼女にそう言って携帯を返した。そしてまた冷めたパスタを口にし始めた。
冷めて伸びたパスタはおいしいはずがない。
「・・・このアドレス・・・彼のアドレスです」
「え?」
「間違いない。だって私彼のアドレスじっと見ていたんだもん」
「で、でもこのアドレスは名前を表示していないけど?」
必死で何か言い訳を考える。あいつ消してなかったのか?
じゃ俺が見たのは一体何だったんだ?それに彼女の言ってることもよくわからない。
安西のアドレスをじっと見ていた?
「でも間違いありません。
彼にメールを送ろうとずっと躊躇ってて毎朝彼のメアドを見ては悩んでいたから
もうアドレスは覚えてたんです。でもおかしい。
アドレス変えたってメール来たし、今までずっと彼とメールしていたはずなのに・・・」
「それはお前がメールをやり取りしていたのが俺じゃなくてそこにいる進藤先輩ってことだよ」
そこにはすごい剣幕をした安西が立っていた。彼女が俺を見る。俺は二人から目を逸らした。
「おかしいと思ったんだ。最近の進藤さんはずっとメールに夢中になっているし、
お前からはメールが来ない。まさかと思って俺とメールしてるのかってのを俺の友達から
お前の友達を通して聞いてもらったら毎日メールしているって言われたし。
お前のアドを消すふりをして全然違うやつのアドを消したりもして
進藤先輩の様子を伺ったりもしたんだ。
それで俺は今日、進藤先輩の後をついてきた。
お前の友達が俺の友達に
『今日、写真渡すために会うこと楽しみにしてるみたい』
って言ってきたのを聞いたからさ。」
「・・・そ、それって・・・じゃあ私は・・・」
「お前はずっとこの人とメールしてきたんだよ」
安西の口から彼女に次々と種明かしがされていく。
でも俺は自分がやったことをまだそれでも正当化していた。
だって安西には梨緒ちゃんを好きな気持ちなんてない。
だから俺を責める理由もないだろうと。
「お前に俺を責める資格なんてないだろう。
だいたい気持ちもないのに期待させるかのようにメアドを教えたお前が悪いんだよ」
「・・・そんなことあなたに言われる筋合いありません」
「梨緒ちゃん?」
「メアドを聞いたのは私です。卒業するからどうしても聞きたかった。
このまま縁が切れてしまうのはどうしても嫌だった。
でもすごく普通に教えてくれたからメール送ってみた。
返事がなかったのはつらかったけれどメールが苦手なんだなって。
そう思っていたときに返事が来た。
うれしかったけど・・・本人じゃない人からの返事なんてもらわないほうがましでした!!」
彼女は俺にそれだけ言ってカバンから財布を取り出し、2000円を置いて店を後にした。
安西は彼女を追いかけて俺はただそこにいることしかできなかった。
翌日、彼女にメールを送ったけれども送信できなかった。彼女はメアドを変えたみたいだ。
安西は俺の専属から離れ、違うやつの専属になった。
俺はようやく自分のやったことが二人を傷つけたことだということに気づいた。