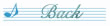向日葵畑に行って向日葵が見たいの。
向日葵畑に行って向日葵が見たいの。沢山の向日葵が見たいの。
そう言った彼女に僕はいつかな、と答えた。
彼女は拗ねたように「いつかっていつ?」と聞いたが、僕は適当にはぐらかした。
無理矢理「絶対に連れて行ってよ!約束よ!」そう指きりさせられた。
僕と彼女の間では、「いつか」というのはいずれは訪れるはずだった。そう、いずれは。
けれど別れは必ずやってくるんだ。僕と彼女との間に交わされた不確かな約束より、
ずっと確実に。
今年の夏も暑い。僕は額に微かに滲み始めた汗を手の甲で拭った。
片手にはアイス――そして、扇風機の前にどんと体を置いて。
むしろ前かがみでこれでもかっていうくらい扇風機に近づいて。
生温い風を感じながら、先日壊れて使い物にならなくなったクーラーを睨み付ける。
ああ、暑い――。体の中から熱が溢れてくるみたいだ。
僕はアイスをかじった。口の中に、甘さと冷たさがいっぱいに広がって、やがて消えて行った。
ああ、なんて儚い。
窓際に置いてある植木鉢の土はカラカラに渇いていて、植物はすっかりと元気を失っていた。
暑いのは僕だけじゃないんだな。
やらないと行けないことは山ほどあった。
8月も半ばに差しかかろうとしているのに、宿題は少しも手をつけていない。
けれどこの熱は僕のやる気まで蒸発させてしまっていた。ああ、やっかい。
まぁ、やる気のせいだけではないんだけども、正直。
夏休みが始まってから連日遊びまわり、今日は久しぶりに家でゆっくりとしている。
そのせいか、時間が経つのがものすごく遅い。
けれど僕は久しぶりの体の休暇を満喫していた。……そんな僕に母は何の容赦もせず、
「ちょっと買い物に行ってきて」と言い放った。
ただ今午後一時。絶好調に気温上昇の時間帯である。
こんなクソ暑いのにそんなの行くわけないだろ――と面と向かって言う事も出来ず、
ぶつぶつ言いながらも僕は買い物へ出かけた。
家の中で感じていた暑さなんか比じゃなかった。焦げる、本気でそう思った。
どちらかと言えば色白の僕だが、真夏の太陽光線のおかげでこんがりといい色に焼けている。
この調子じゃもっと黒くなるかもしれない。
上から降って来る日差しも暑いが、アスファルトに跳ねかえって僕にぶつかってくる熱も熱い。
つまり、あつい。
頭がおかしくなりそうだ。
僕はふと足を止めた。どこかの金持ちそうな家の花壇に、向日葵がぽつんと咲いていた。
他の植物は強すぎる日差しでだめになってしまったらしく、
元気なのはこの一輪の向日葵だけだった。
じっと、向日葵を見つめる。
黄金色の大きな花はぐったりするどころかむしろ生き生きと咲き誇っていた。
先ほど水を与えたばかりなのか、花弁には水滴がついていた。
太陽の光を浴びてキラキラと輝いている。
『向日葵畑に行って向日葵が見たいの』
ふと、彼女とした約束が思い出された。
去年の夏交わした約束。果たされる事無く、今も僕の胸に佇む……。
つくづく幸せを怖いと思う。何の根拠もなく、永遠を信じることの出来る幸せ。
隣にいるのが当たり前だと信じ込んでしまう幸せ。
失ってしまった瞬間、その場に立っていられなくなるほどの幸せ――。
「あ……」
聞き覚えのある声の方向に顔を向ける。僕は目を見張った。
どうして?まっさきに頭に浮かんだのはその一言。
「……久……ぶりだね……」
そこにいたのは、別れたはずの彼女だった。
「元気してた?」
「……ああ」
なるべく驚きを表に出さぬよう努力した。
けれど心臓はバクバクと規則正しくも激しく動き、今にも飛び出そうだ。
「あれからもう1年も経つのね……」
「……ああ」
彼女は遠くを見ながらふと目を細めた。
動揺と驚愕で言葉が出てこない。伝えたい言葉は、沢山沢山あるはずなのに。
1年前、あんな別れ方をしてしまった彼女へ、伝えたい言葉。
「ごめんな」
「え?」
「――約束、守れなくて」
僕は頭を下げた。拍子に、汗がアスファルトへ落ち、弾けた。
彼女の足先だけをじっとみていた。翳りのないアスファルトにぽつんと存在する、彼女の足。
熱さの所為だろうか、クラクラした。
「謝らないで」
しばらくの沈黙の後に、彼女は言った。僕は顔を上げた。
透き通るように白い彼女の肌に伝うのは、涙。
「覚えていてくれてありがとう」
彼女は微笑んだ。
「それに、約束は――果たされたんじゃない?」
そう言って彼女が指差した先には、一輪の向日葵。
「まぁ、沢山の向日葵じゃあないけどね」
彼女がそっと、慎重に向日葵に触れる。向日葵は少しも揺れなかった。
ふふふ、と笑う彼女が悲しくて。僕は拳を握り締めた。
「でも、貴方と見れてよかった。向日葵」
我慢できずに僕は彼女を抱きしめた――けれど、
僕が掴めたのはせいぜい空気だけだったのだろう。
僕の腕の中には何もなかった。そう、何も。
「う……うわぁぁぁっぁぁ!!!!!!」
急に悲しみが込み上げてきて、僕は泣いた。太陽が僕を焦がす。
汗が額からこめかみに伝い、涙と混じる。
そしてそれは、向日葵の花弁に落ち、弾けた。向日葵が微かに揺れる。
僕は足元を見た。くっきりと描かれた影。それを見て、余計に涙が出た。
なぁ、君は――僕といて幸せだったのかな?
尋ねても返事など返ってこない。ただ、二人ですごした鮮やかな日々が思い出された。
彼女の笑顔が。僕の笑顔が。
もう二度と戻ってはこない日々。
*FIN*
やった〜珠羽ちゃんから小説いただいちゃいました v(≧∇≦)v
素晴らしい文才力満点でもう読んでて感動の渦に包まれましたね!!
切ないな〜><
でも切なさの中にもやっぱり素晴らしさが出てます☆☆
さぁ〜珠羽ちゃんの文章の魅力をもっと感じたい人は
彼女のサイトにLet's go〜 o(≧∇≦o)(o≧∇≦)o